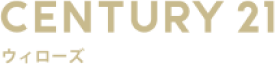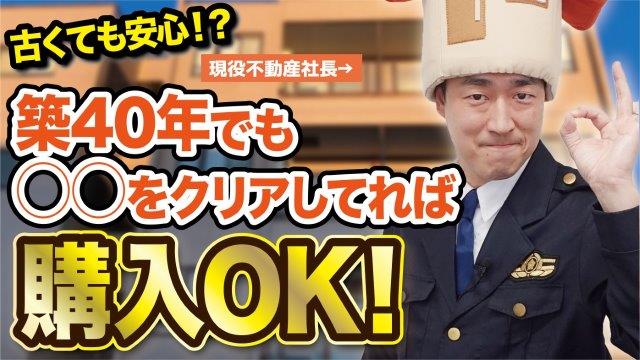はじめに
築年数が古い中古マンションに対して、「耐震性は大丈夫か」「建物の劣化が進んでいるのではないか」「そもそもどのくらい住めるのか」といった不安や疑問を抱く方は少なくありません。
中古であるがゆえに、ネガティブなイメージを持たれることもあります。
マイホームの購入にあたっては、資産価値、住宅ローン、生活環境など、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、これらすべてにおいて築年数が大きく関わっています。
マンションにも寿命があるため、築年数がどのように影響するのか、また、そもそも寿命はどの程度なのかを理解せずに購入してしまうと、後に大きな負担や後悔を招く可能性があります。
そこで本記事では、「中古マンションの築年数」について解説していきます。
本編
マンション寿命の基礎知識と寿命を左右する要因
法定耐用年数・物理的耐用年数・経済的耐用年数の違い
マンションの寿命を考える際には、「法定耐用年数」「物理的耐用年数」「経済的耐用年数」という3つの異なる指標を理解することが重要です。
まず、法定耐用年数は税法上の概念で、減価償却の計算に用いられる年数を指します。
鉄筋コンクリート造のマンションでは47年と定められていますが、これは実際の居住可能期間を示すものではありません。
一方、物理的耐用年数は建物の構造や材料が物理的に使用可能な期間を示し、適切な修繕を行えば100年以上使用できる場合もあります。
そして、経済的耐用年数は市場での資産価値や利用価値が保たれる期間を指し、築年数の経過や立地条件、需要の変化によって短くなることもあります。
これら3つの耐用年数を総合的に理解することで、マンションの寿命をより正確に見極めることができます。
マンション寿命に影響する主な要因
マンションの寿命を左右するのは、築年数だけではありません。
定期的なメンテナンスや長期修繕計画を元に実施される大規模修繕工事も寿命に大きな影響を与えます。
大規模修繕工事とは、屋根・外壁・配管・共用部などの劣化部分を修繕し、建物の機能と安全性を維持するための重要な工事です。
日本では一般的に12〜15年ごとの実施が推奨されています。
修繕がしっかり行われているマンションは、築年数が古くても良好な状態を維持でき、寿命を大きく延ばすことが可能です。
マンションの管理状況や修繕積立金の充実度も、寿命を考える上で重要なチェックポイントとなります。
管理組合が機能しており、計画的に修繕が実施されている物件であれば、築年数が経過していても安心して暮らせます。
一方、修繕が滞っている場合は、建物の劣化が進み、結果として寿命が短くなるリスクもあります。
築年数が古くなるにつれて、配管や防水、外壁など修繕が必要な箇所が増え、それに伴い維持管理コストも増加する傾向にあります。
築古マンションでは、給排水管がコンクリートの内部に埋め込まれているケースもあり、その場合は配管の交換や修繕が困難になります。
配管が床下に設置されているなど、メンテナンス性に優れた構造かを確認することが重要です。
外壁や共用部のコンクリートにひび割れ、鉄筋の露出、塗装のはがれなどの劣化が見られる場合、構造的な耐久性に影響する可能性があります。
こうした劣化の有無は、マンションの寿命を判断するうえで大きな手がかりになります。
また、立地条件や施工品質も大きく関係します。
例えば、海に近い塩害地域では、海風に含まれる塩分がコンクリートや鉄筋を劣化させ、寿命を縮める可能性があります。
また、日照不足の環境では湿気がこもりやすく、外壁や共用部分の劣化が早まることもあります。
さらに、建築時の施工品質の差も耐久性に影響し、同じ築年数でも寿命の長さに大きな差が生じる場合があります。
このため、購入前には立地や施工の実績もあわせて確認することが大切といえるでしょう。
旧耐震基準と新耐震基準の違い
日本では、1981年に新耐震基準が導入され、それ以降に建築されたマンションは、地震に対する耐震性が高いと評価されています。
中古マンションを購入する際は、「1981年6月以降(新耐震基準施行後)に建てられているか」を一つの基準として確認することが重要です。
なお、1981年以前に建築された旧耐震基準の物件でも、適切な耐震補強が施されていれば、安全に住み続けることは十分可能です。
過去の修繕履歴や耐震補強工事の有無も忘れずにチェックしましょう。
平均寿命と最新技術の動向
国土交通省の調査によると、鉄筋コンクリート造(RC造)のマンションの平均寿命は約68年とされています。
しかし、これはあくまで平均値であり、適切な管理や修繕を行えば100年以上使用できるケースも珍しくありません。
近年では、水セメント比を下げてコンクリートの強度を高めたり、施工時に均等に流し込む技術を採用することで、120年〜150年の寿命を目指す長寿命マンションも登場しています。
このように、技術革新がマンションの寿命を飛躍的に伸ばしているのが現状です。
中古マンションの築年数と資産価値の関係
築年数が進むと資産価値は下がる傾向
中古マンションは、一般的に築年数の経過とともに建物が劣化し、それに伴って価格が下落する傾向があります。
これは初めて不動産を購入する方でも、感覚的に理解しやすい現象です。
公益財団法人東日本不動産流通機構が発表している「中古マンションの築年帯別平均平米単価」のデータでも、築年数が進むにつれて価格が下がっていく傾向が明らかになっています。
特に築20年〜30年のあたりでは、価格の下落幅が大きくなるのが特徴です。
(参考)東日本不動産流通機構の中古マンション築年帯別平均平米単価
築30年超の一部マンションでは価格上昇も
一方、築30年以上のマンションにおいては、価格が上昇に転じているケースも確認されています。
これは、築40年前後の物件が都心部など立地の良い場所に多く存在し、買取再販業者によるリノベーションが加わることで資産価値が高まり、価格が上がっているためです。
ただし、データ上は築41年以上の物件が一括りで集計されているため、旧耐震基準に該当する築44年以上(2025年時点)の物件かどうかは個別に確認する必要があります。
新耐震基準を満たしていない物件は、価格の下落幅が大きくなる傾向があるため注意が必要です。
管理体制の良し悪しが寿命と資産価値を左右する
築年数の経過によって資産価値が下がる傾向はあるものの、すべてのマンションが同じように価格下落するわけではありません。
実際の価格の維持・下落の度合いは、マンションの管理体制によって大きく異なります。
適切な維持修繕が行われ、管理組合が機能しているマンションは、築年数が経過しても建物の状態を良好に保ち、資産価値の下落を抑えることが可能です。
例えば、築20年以上のマンションでも、外壁補修や配管交換などの定期的な修繕が行われ、修繕積立金がしっかり積み立てられている物件は、取引価格にも良い影響を与える傾向があります。
リノベーションと資産価値
中古マンションの購入を検討している方の中には、「リノベーションを施せば築年数が経っていても資産価値を維持できるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、最新設備への変更や間取りの変更により、生活スタイルに合った魅力的な住空間を実現できるため、リノベーション済み物件は市場でも一定の人気があります。
リノベーションすることで居住性や見た目は向上しますが、必ずしも資産価値が上がるとは限りません。
リノベーションにかけた費用を売却価格で回収できるかどうかは、物件の立地や市場環境、他の競合物件との価格差など、複数の要因に左右されます。
特に人口減少地域や競合物件が多いエリアでは、リノベーション後でも思ったほど価格が伸びないケースもあるため、過度な期待は禁物です。
リノベーションを検討する際には、建物構造や法的規制に配慮しなければならない場合があります。
特に築古マンションでは、耐震補強や断熱性能など外部構造に関する改修が必要となることがあり、個人の判断だけでは対応が難しいケースもあります。
そのため、専門家のアドバイスを受けたうえで、リノベーションの費用対効果を慎重に見極めましょう。
住宅ローン審査における築年数と寿命の関係
新耐震基準物件は審査に通りやすい
住宅ローンの審査において、築年数が影響するという話を耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際、住宅ローンの審査では「築年数」および「マンションの寿命」が重要な審査項目の一つとされています。
特に注目すべきは、建物が「旧耐震基準」か「新耐震基準(1981年6月以降)」のどちらで建てられているかという点です。
新耐震基準を満たしたマンションであれば、築年数が多少古くても住宅ローン審査に大きな影響を及ぼすことは少ない傾向にあります。
これは、住宅ローンが物件の担保価値を基準に審査されるためです。
耐震性が高く資産価値が維持しやすいと判断されるため、金融機関からの評価も良好です。
旧耐震基準物件の審査は厳しめ
一方、旧耐震基準の物件は耐震性の面で懸念されやすく、金融機関からの担保評価が低くなる傾向があります。
そのため、審査が厳しくなったり、借入可能額が減額されたりすることがあります。
また、金融機関によっては旧耐震基準の物件に対して融資しないケースもあるため、購入前に確認が必要です。
住宅ローン審査では、借入期間や金利、融資可否の判断材料として、「1981年6月以降(新耐震基準施行後)に建築されたか」が重要な基準となります。
投資用ローンでは築年数が審査に直接影響
投資用ローンにおいては、築年数がより直接的に影響します。
これは、物件の収益性が重視されるためです。
築古の物件は賃料下落や空室リスクが高く見なされるため、審査が厳しくなる傾向があります。
築古マンションで住宅ローンを組む際の注意点
築古のマンションでも住宅ローンを組むことは可能ですが、いくつかの注意点があります。
借入期間に制限がある
築年数が進んだ物件では、金融機関が残存耐用年数をもとに返済期間を短く設定することがあります。
特に築40年を超える物件では、ローン審査がさらに厳しくなります。
また、建替えが難しいエリアや再建築不可の土地にある場合は、金融機関が資金回収リスクを懸念し、融資条件が厳しくなることがあります。
借入期間が短縮されると、月々の返済額が増える可能性があるため、無理のない資金計画や頭金の準備が重要です。
リフォームローンやリノベーションローンの併用を検討
築古マンションでは、購入後に修繕が必要となるケースが多く見られます。
こうした場合、リフォームローンやリノベーションローンを併用することで、物件価格と改修費用を合わせて借り入れられます。
ただし、住宅ローン控除の対象となるのは住宅ローンのほうであり、リフォームローンと併用する場合は控除の条件や対象に注意が必要です。
また、リフォームローンは金利が高く設定されていることがあるため、トータルの返済額を事前に確認しておくことが大切です。
金利条件の比較も欠かせない
築古物件では、金融機関が担保評価を低めに設定する場合があるため、住宅ローンの金利が高くなる可能性があります。
金利は返済総額に直結するため、複数の金融機関で条件を比較し、最も有利なローンを選ぶことが重要です。
不動産会社に勧められた金融機関のみで手続きを進めるのではなく、面倒でも複数の選択肢を確認することが将来的な負担を軽減します。
新耐震基準のマンションを選ぶと有利
1981年6月以降(新耐震基準施行後)の新耐震基準に則って建設されたマンションは、住宅ローン審査においても優遇されやすい傾向があります。
耐震性能の高さから金融機関の担保評価も安定しており、借入条件が良好となるケースが多くなります。
旧耐震基準のマンションであっても、「耐震基準適合証明書」が取得されていれば、一定の安全性が認められ、ローン審査において新耐震と同様に取り扱われることがあります。
検討中の物件が旧耐震基準である場合は、この証明書の有無を必ず確認しましょう。
築年数別マンションの特徴とメリット・デメリット
築10年以内|最新設備と高い再販性
【特徴】
築10年以内のマンションは、耐震性・防災性能・省エネ性に優れており、スマートホーム化された最新設備を備えた物件が多い点が特徴です。
オートロック、監視カメラ、宅配ボックスなどの防犯設備が整っており、スマートフォンと連動した管理システムも導入されています。
【メリット】
・新築に近い内装と設備
・メンテナンス費用が抑えられる
・再販性が高く、資産価値の下落リスクが低い
・ローン審査が有利で、住宅ローン控除の恩恵も受けやすい
【デメリット】
・新築に近い価格で割高
・売り物件が少なく、希望条件に合う選択肢が限られる
築10年〜20年|性能と価格バランスの良さ
【特徴】
この時期に建てられたマンションは、防犯性・エコ性能の向上が図られており、バリアフリーやオール電化対応の物件も増えています。インターネット対応や共有施設の整備も進んでいます。
【メリット】
・価格が安定し、コストパフォーマンスが高い
・初回の大規模修繕が完了している物件が多い
・省エネ・防犯性の高い設備が導入されているケースも
【デメリット】
・経年劣化による水回り・設備の交換費用が発生する場合がある
・入居後すぐに修繕工事が始まる可能性もある
(参考)【中古マンション】築20年マンション購入のリスク・重視すべき3つの判断基準を徹底解説 | 武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズ
築20年〜30年|価格が手頃で選択肢が広がる
【特徴】
この時期はバブル崩壊後の物件が多く、品質向上を目的とした法律(住宅品確法)も施行されました。
オートロックや監視カメラも標準化され、バリアフリー対応も進みつつあります。
【メリット】
・価格が手頃で広めの物件が狙える
(公益財団法人 東日本流通機構の中古マンション築年帯別平均平米単価のデータでも、
20年〜30年になると価格が下がっている)
(参考)東日本不動産流通機構の中古マンション築年帯別平均平米単価
・大規模修繕が1〜2回済んでおり、管理状況を確認しやすい
【デメリット】
・リフォームが必要なケースが多い
・金融機関によっては住宅ローンの借入期間が短縮され、返済負担が重くなる可能性がある
(参考)【中古マンション】築30年のマンション購入しても大丈夫? | 武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズ
築30年〜40年|立地の良さと修繕負担の増大
【特徴】
バブル期に建てられたマンションが多く、立地の良さが大きな魅力です。
広い間取りのファミリー向け物件が多い一方、老朽化した設備やエレベーター未設置の建物も見られます。
【メリット】
・価格が下がりきっており、購入後の下落リスクが少ない
・好立地・広い間取り・将来的なリノベーションに向いている
【デメリット】
・設備の老朽化により修繕費がかさむ可能性
・管理組合の高齢化により、意思決定が停滞しやすい
・修繕積立金不足や追加徴収のリスクあり
(参考)【中古マンション】築40年のマンション購入しても大丈夫? | 武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズ
築40年以上|価格の安さと立地の魅力もあるが慎重に検討
【特徴】
高度経済成長期に建設された物件が多く、建築当初は「量の確保」が優先されていた時代です。
旧耐震基準の物件も多く、設備や構造も現代基準には及びません。
【メリット】
・非常に手頃な価格で購入可能
・都心部や駅近など、好立地の物件が多い
・予算を抑えてリノベーションに投資しやすい
【デメリット】
・旧耐震物件が多く、住宅ローン審査が通りにくい
・再販価値が低下する可能性がある
・建て替えの検討が必要なケースがあり、長期居住にリスクを伴う
(参考)築50年の中古マンション購入ガイド:リスクと資産価値を徹底解説
寿命を迎えたマンションの3つの選択肢
建て替える
マンションの寿命を迎えた際の代表的な選択肢が建て替えです。
建て替えには区分所有者全員の合意が必要となり、実際には法律上5分の4以上の賛成が求められます。
耐震性や設備の老朽化を一新できる一方、解体・新築の工事費用や一時的な仮住まい費用など、居住者にとって大きな負担が発生します。
デベロッパー等へ売却する
区分所有者が合意のうえで、デベロッパーや不動産会社に土地・建物を一括して売却する方法です。
デベロッパー側が建物を解体し、新たな開発を行うケースが一般的です。
解体費用は売却価格から差し引かれる場合が多いですが、立地条件によっては好条件で売却できる可能性もあります。
そのまま住み続ける
寿命に近づいたマンションでも、適切な修繕と管理を行いながら住み続ける選択肢もあります。
耐震性や設備の安全性が確保されている場合は、物理的には居住が可能です。
ただし、修繕費用が増大する傾向や将来的な建て替え・売却の難しさを考慮し、長期的な維持計画を立てることが重要です。
マンションの寿命を迎えた際には、資産価値だけでなくライフスタイルの変化や住み替え計画も視野に入れて検討することが重要です。
「中古マンションの築年数の限界」不動産のプロの見解
「中古マンションの築年数の限界」不動産のプロの見解として、ここでは、
・新耐震基準を満たす物件が評価される理由
・精神的安心と資産価値の維持が購入判断のポイント
・築44年以上でも住めるが、条件の確認が必要
について、解説していきます。
新耐震基準を満たす物件が評価される理由
2025年時点で、新耐震基準の導入からおよそ44年が経過しています。
この基準を満たすマンションは、地震に対する安全性が高いことが特徴です。
そのため、購入後の精神的な安心感を得られるだけでなく、住宅ローンの審査に通りやすい、再販売時の資産価値を維持しやすいといった実利的なメリットも多く存在します。
新耐震基準のマンションは、市場においても高く評価されており、将来的に賃貸や売却を検討する際にも安定した需要が見込めます。
金融機関も耐震性を担保できる物件には融資条件を柔軟に対応する傾向があるため、結果として購入者にとって有利な選択肢となります。
精神的安心と資産価値の維持が購入判断のポイント
中古マンションを購入する際には、精神的な安心感と資産価値の維持の両方を考慮することが重要です。
特に新耐震基準をクリアしている物件は、この2点を満たしやすいため、築年数が進んでいたとしても購入価値が高いといえます。
築44年以上でも住めるが、条件の確認が必要
築44年以上のマンションであっても、住めないわけではありません。
実際には、適切なメンテナンスや修繕、管理が行われていれば、築50年、築60年の物件でも安全に居住することが可能です。
国土交通省が公表しているデータによれば、現在のRC(鉄筋コンクリート)構造のマンションの寿命は68年とされています。
このように、マンションの寿命は法定耐用年数ではなく、管理や修繕の状況によって大きく左右されるというのが実情です。
しかし、住宅ローンや再販性、精神的な安心感を考えた場合に新耐震基準を満たす物件、つまり築44年以内の物件を購入することがおすすめといえるでしょう。
まとめ
中古マンションを購入する際、築年数は物件選びにおいて最も重要な要素の一つです。
築年数の経過により、建物の耐久性や住宅ローンの審査、さらには資産価値にも影響が出るため、慎重な判断が求められます。
特に、新耐震基準に切り替わる「築44年」は、マンションの寿命という観点から見ても、検討時のひとつの目安になるといえるでしょう。
ただし、築44年以上の物件やそれ以前に建てられたマンションがすべて問題であるというわけではありません。
物件ごとの管理状況や修繕履歴、構造上の特性を十分に把握したうえで、今回ご紹介した注意点や特徴を参考に、ご自身に合ったマンションを検討いただくことが大切です。
不動産のご相談ならウィローズ
資金計画の立て方が分からない、
相談できるいい会社や担当者がいないという方はぜひ
武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せください。
お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。お気軽に公式LINEからご相談ください。