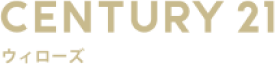はじめに
マイホームとして新築一戸建てを建てる場合には、まず土地を購入する必要があります。その際には「建ぺい率」という規制があり、土地ごとに建築できる建物の面積が異なります。土地は高額であるため、同じ敷地面積でもできるだけ広い建物を建てたいと考える方が多いでしょう。
本記事では、建ぺい率・容積率の基本的な考え方と、より広く建てるための工夫について解説していきます。
本編
建ぺい率の基本|計算方法と用途地域別の基準
建ぺい率の計算方法(事例つき)
建ぺい率とは、土地に対して一階部分で建築可能な面積を示す数値であり、「%」で表されます。
建ぺい率の計算式
建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
例えば、同じ土地の面積でも建ぺい率が高ければ、ワンフロアでより大きな建物を建てられます。
建ぺい率が40%の土地と80%の土地を比べると、ワンフロアで建築できる面積はおよそ倍の差が生じます。

建ぺい率と建築可能面積の関係|100㎡土地の計算例
建ぺい率は、ワンフロアの広さに直接関わるため、リビングなどの居住空間の広さに大きな影響を与えます。
具体的なイメージが湧くよう、建ぺい率ごとの建築可能面積を下図にまとめました。

※帖数換算は 1帖=約1.62㎡(一般的な畳サイズ)で概算。
逆に、ワンフロアで24帖を確保したい場合を考えると、建ぺい率が40%のエリアでは土地が100㎡必要となります。
一方、建ぺい率が80%のエリアであれば、理論上50㎡の土地でも同じ24帖を確保できます。

東京のように土地価格が高額な地域では、一坪増えるだけで200万〜300万円程度費用が増えることもあります。そのため、限られた予算で広い建物を建てたい場合には、建ぺい率が高い土地を選ぶことで総額を抑えられます。
反対に、大きな庭を確保したい場合には、建ぺい率が低い土地を選ぶことが適しています。
用途地域ごとの建ぺい率・容積率早見表
建ぺい率と容積率は、土地が属する用途地域によって異なります。
用途地域とは、都市計画法で定められたエリア区分のことで、住居系・商業系・工業系などの種類があります。それぞれの地域で、住環境の保護や街並みの整備を目的に上限が決められています。
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 第一種低層住居専用地域 | 30〜60% | 50〜200% |
| 第一種中高層住居専用地域 | 40〜60% | 100〜200% |
| 第一種住居地域 | 60% | 200〜400% |
| 商業地域 | 80% | 200〜400% |
上記のように、住宅系は低め/商業系は高めに設定されるのが一般的です。購入前に用途地域と合わせて上限値を必ず確認しましょう。
建ぺい率アップ・緩和の条件
建ぺい率が10%アップする条件
建ぺい率には優遇措置があり、条件を満たすことで数値が10%上乗せされる場合があります。
・角地緩和(角地の場合+10%)
・防火地域または準防火地域で、耐火または準耐火建築物を建てる場合(+10%)
例えば、図面に建ぺい率60%と記載されていても、準耐火建築物とすることで建ぺい率70%まで建築できるケースが多くあります。
建ぺい率10%アップで建物の大きさはどれくらい変わる?
土地が100㎡なら、建ぺい率10%の差は10㎡(約6帖分)の差となり、一部屋分の広さを確保できます。
角地緩和+耐火建築物の組み合わせで最大20%アップも可能。
防火地域で建ぺい率が実質無制限になるケース
指定建ぺい率が80%の地域で、防火地域かつ敷地内すべての建築物が耐火構造であれば、建ぺい率に上限がなくなり敷地いっぱいに建築可能です。
※この緩和は地域指定や建物構造条件など自治体の運用で異なるため、必ず建築指導課で確認してください。
建ぺい率に含まれない部分|軒・バルコニー
出幅1m以内のバルコニー・軒・庇は建ぺい率に算入されません。
建ぺい率いっぱいの設計でも90cm程度のバルコニーを追加可能です。

容積率の基本|計算方法と建ぺい率との違い
容積率は「敷地面積に対する延床面積(各階の床面積を合計した数値)の割合」を表します。
建物全体のボリュームをコントロールするための指標で、都市計画法に基づいて用途地域ごとに上限が定められています。
容積率の計算式
容積率(%)= 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100
建ぺい率と容積率の違いを整理すると次の通りです。
| 項目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 制限するもの | 建築面積 (1階部分の広さ) |
延床面積 (建物全体の合計床面積) |
| 目的 | 建物の敷地占有率を制御し、空地や採光を確保すること | 建物の総ボリュームを制御し、街並みや人口密度を調整すること |
| 影響 | 庭や駐車場の広さに影響 | 建物の階数や部屋数に影響 |
| 設計時のポイント | 平屋や1階部分の広さを考える際に重要 | 2階建・3階建などの延床計画を立てる際に重要 |
容積率の計算方法(事例つき)
容積率は、敷地全体の延床面積を制限するため、設計段階で必ず確認すべき指標です。
事例:100㎡の土地で容積率が200%の場合
・延床面積の上限は「100㎡ × 200% = 200㎡」
・2階建なら1フロア100㎡ずつ、合計200㎡の建物が建築可能。
容積率と建物階数の関係(2階建・3階建のシミュレーション)
容積率は階数計画に直結します。以下のシミュレーション例を参考にしてください。
容積率と建物階数の関係
| 建物タイプ | 1フロアの広さ | 合計延床面積 | ポイント |
| 2階建 | 100㎡ | 200㎡ (容積率200%) |
各階がゆったり、広いリビング向き |
| 3階建 | 約66㎡ | 198㎡ (容積率200%内) |
各階がコンパクト、部屋を分けたい家庭向き |
容積率アップ・緩和の条件
道路幅による容積率制限(用途で0.4/0.6の違いに注意)
容積率は「用途地域で定められた数値」と「前面道路幅員に基づく数値」のうち低い方が適用されます。
前面道路による上限は、原則 幅員×0.4、ただし近隣商業・商業・準工業地域では 幅員×0.6 が上限です。
例:道路幅6m×0.6=360% → この数値と用途地域指定の容積率の小さい方が採用されます。
地下室・ビルトインガレージ・ロフトの特例
地下室:延床面積の3分の1まで容積率から除外
ビルトインガレージ:延床面積の1/5まで除外
ロフト:下階面積の1/2以下かつ天井1.4m以下なら除外
マンション建替えにおける容積率緩和特例
老朽化したマンションを建て替える際には、容積率の緩和特例が適用される場合があります。
これは、耐震性不足のマンションや老朽化が進んだ建物の再生を促すために設けられた制度で、一定の条件を満たすと特定行政庁の許可により容積率の上限が緩和されます。
この特例を利用すれば、従来の容積率制限を超えて建築できるため、敷地を有効活用しながら住戸数を増やすことが可能となります。
結果として、建替え事業の採算性を高め、住民の合意形成を進めやすくする効果も期待できます。
建ぺい率や容積率の一般的な制限だけでなく、このような再開発や建替えに関する緩和制度を活用することで、都市部におけるマンション再生の選択肢が広がります。
建ぺい率・容積率の調べ方
土地を購入する際や建築計画を立てる際には、対象となる敷地の建ぺい率や容積率を正しく把握することが不可欠です。
これらの数値は、自治体が定める都市計画に基づいて決められており、地域や用途地域によって異なります。
主な調べ方は以下のとおりです。
自治体の公式ホームページや都市計画図の確認
多くの自治体では、建ぺい率・容積率を用途地域ごとに公開しています。
役所の都市計画課や建築指導課に問い合わせ
現地の窓口で、最新の建築基準や制限内容を直接確認することができます。
不動産会社や建築士に相談
販売図面や設計プランには建ぺい率・容積率が記載されていることが多く、専門家に相談することで誤解や見落としを防げます。
建ぺい率・容積率をオーバーした場合のリスク
建ぺい率や容積率は法律で定められた建築制限であり、これを超えて建物を建てることはできません。
万が一、オーバーして建築した場合には以下のようなリスクが発生します。
建築確認が下りない
建築計画が建ぺい率・容積率を超えていると、建築確認申請が認可されず、建物を建てられません。
違反建築物とみなされる
制限を超えて建築した場合、違反建築物として是正命令や使用制限を受ける可能性があります。
売却時にも大きなマイナス要因となります。
資産価値が低下する
違反状態の物件は金融機関の融資対象外となることが多く、担保価値が下がるため売却や相続時に不利になります。
建ぺい率・容積率以外に確認すべき建築制限
建築計画を立てる際には、建ぺい率や容積率のほかにも複数の建築制限を確認する必要があります。
代表的なものとしては以下のような規制があります。
斜線制限
建物の高さや形状を制限するもので、道路や隣地から一定の角度内に収まるように建築する必要があります。
日影規制
周辺住宅の日照を確保するため、建物の高さや配置を制限する規制です。
高さ制限や北側斜線
低層住宅地では、建物が過度に高くならないように規制されています。
これらの規制は、建ぺい率や容積率を満たしていても建築できる形や大きさに影響を与えます。
土地を購入する際には、建ぺい率・容積率だけでなく、その他の建築制限についてもあわせて確認しておくことが重要です。
よくある質問(FAQ)
建ぺい率がオーバーしたらどうなる?
建ぺい率を超えて建築すると、違反建築物とみなされます。建築確認申請が通らないのはもちろん、完成後に是正命令や使用制限を受ける可能性もあります。
また、融資が下りにくくなったり、売却が難しくなるなど資産価値にも大きな影響を及ぼします。
容積率ギリギリでも建てられる?
容積率の上限を守っていれば、数値ギリギリまで建てることは可能です。
ただし、斜線制限や日影規制など、他の建築制限によって設計が制約される場合があります。そのため、実際には容積率いっぱいに建てられないケースもあるため注意が必要です。
建ぺい率・容積率を調べる方法は?
建ぺい率や容積率は、自治体が公開している都市計画図やホームページで確認できます。
また、役所の都市計画課や建築指導課に問い合わせる方法や、不動産会社・建築士に確認する方法もあります。土地購入前に最新情報を確認することが重要です。
古家付き土地を買った場合、再建築できる?
古家付きの土地を購入した場合でも、建ぺい率や容積率の規制が現在の基準と異なっていることがあります。古い建物が既存不適格となっている場合、同じ規模の建物を建て直せない可能性があります。
購入前に再建築の可否を確認しておく必要があります。
建ぺい率と容積率どちらを優先すべき?
建ぺい率は建物の「建築面積」、容積率は「延床面積」に影響します。どちらも重要ですが、限られた土地で広い居住空間を確保したい場合は容積率、庭や駐車場を確保したい場合は建ぺい率の確認が特に重要になります。
最終的には家族のライフスタイルや建築プランに応じて、両方をバランスよく考慮することが大切です。
まとめ
建ぺい率はワンフロアの広さ、容積率は建物全体のボリュームを規制する数値であり、土地活用や家づくりにおいて重要な基準です。
これらは用途地域や道路幅などの条件によって変動し、地下室やビルトインガレージ、小屋裏収納などには容積率から除外できる特例もあります。
さらに、角地や準防火地域での準耐火建築物など、建ぺい率が10%以上緩和されるケースも存在します。
建築計画を進める際には、建ぺい率・容積率の基本だけでなく、各種の緩和措置や制限も確認し、専門家へ相談しながら計画を立てましょう。
不動産のご相談ならウィローズ
資金計画の立て方が分からない、
相談できるいい会社や担当者がいないという方はぜひ
武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せください。
お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。お気軽に公式LINEからご相談ください。