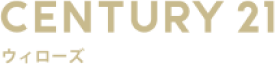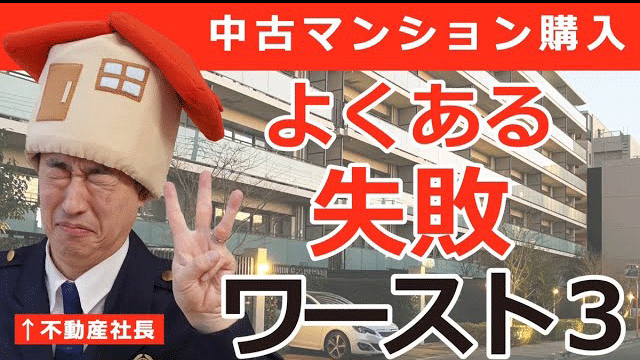はじめに
そろそろ実家の相続について考えないといけないけど、何から調べれば良いかわからない…
相続する実家を売却すべきか、賃貸に出すべきか、リフォームして住むべきか迷っている。
そのような悩みを抱えていませんか?
実家の相続はいつ発生するかわかりません。
両親がまだ健康な場合は、相続について抵抗がある方も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産を相続していく上で、知るべきことや注意点など事前に情報収集することが大切です。
今回は、不動産のプロがやってはいけない実家の相続の注意点や売却の流れなどを詳しく解説します。
本編
実家を相続するにはどうする?5つの手順
実家の相続をするだけなら、所有権を移転するだけでいいのでは?と考える方も多いでしょう。
しかし、実家の所有権を移転するには、数多くの手続きを経て、相続の登記を完了する必要があります。
相続する財産の価値が一定以上あると、特定の期間内に税務署に相続を申告した上で相続税を納税しなければなりません。
期限内に申告と納税をしなければ、追徴課税をされてしまうため注意が必要です。
無駄な税金を払わずに済むように、相続の最低限の知識として、相続税について理解しておくことが大切です。
実家を相続する流れは次の5つの手順です。
①遺言書が存在するか確認する
②相続財産と相続人の認定
③遺産分割協議
④相続財産の名義変更
⑤相続税の申告と納税
遺言書が存在するか確認する
亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
相続は、原則として遺言書通りに実行されます。
遺言書が残された場合は、記述の内容で相続を進めていきます。
遺言書の保管場所は、自宅や銀行の貸金庫、公証人役場に保管しているなど様々です。
亡くなった方が生前遺言書を残しているのか、どこに保管しているのかを聞いておかなければ、後々探すのに苦労してしまいます。
あらかじめ遺言書があるのかを確認しておきましょう。
遺言書が残っていない場合は、相続財産と相続人の選定を行います。
●相続財産の種類
●相続の価格
●相続人の人数
を確認し、適正に相続の引き継ぎと相続ができるようにします。
相続財産は、不動産や現金のようなプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も相続の対象になります。
プラスとマイナスの財産があるか確認する必要があります。
相続財産と相続人の認定
戸籍や住民票の除票をたどり、法定相続人を確定します。
場合により、隠し財産や隠し子がいるケースもあり、個人で確定するのは難しいため、司法書士や弁護士にお願いすると安心です。
遺産分割協議
相続人全員で遺産の分割方法を協議します。
遺産分割協議では、法定相続分に応じ、”どの遺産を誰が引き継ぐか”取り決めたことを遺産分割協議書として書類に残します。
書類に全員の実印を押して、印鑑証明書を添付した上で全員が原本を所有して協議は終了です。
この遺族分割協議書は相続登記に必要な書類のため、この時点で実家の所有権移転・登記ができる状態になります。
なお、実家の相続登記には登記免許税という税金が課税されます。
課税額は実家の固定資産税評価額により決定します。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、時間を要します。
不動産は現金のように均等に分けることができず、誰がどの不動産を相続し、どのように引き継ぐのか揉めるケースが多いです。
相続人同士のトラブルを避けるには、不動産の分割方法を知っておく必要があります。
不動産の分割方法は、以下の4つの方法があります。
●現物分割:土地を分割する方法(各相続人の相続分を分割する)
●代償分割:相続分よりも価値の高い実家を一人の相続人が相続し、現金や有価証券などで他の相続人に補填する方法
●換価分割:実家を売却し、その売却資金を相続人で均等に分割する方法
●共有分割:相続人が相続分に応じて実家を共有名義にする方法
相続人同士で話し合うことができれば、遺産分割協議がスムーズに進むことが多いです。
相続財産が不動産だけの場合は、実家に住みたい相続人が代償分割を選択するのも選択肢の一つになります。
相続人同士の考えを尊重しながら、話し合いをするのが、遺産分割協議をスムーズに進めるコツです。
相続財産の名義変更
上記が完了したら、預貯金名義や車の名義も変更が可能になります。
相続税の申告と納税
遺産の名義変更も進めると同時に、税務署に相続税の申告を行います。
納税を行い相続税の手続きは完了です。
相続時に課税される税金の種類
相続時に課税される税金である
●相続税
●登録免許税
を解説していきます。
相続税
相続財産が基礎控除を超えた場合に、相続税が課税されます。
相続税での基礎控除の計算方法は以下の通りです。
相続税の基礎控除額
3,000万円+法定相続人の数×600万円
例えば、法定相続人が3人いた場合
3,000万円+3×600万円=4,800万円
になります。
この金額までの相続財産であれば相続税はかかりません。
相続税は相続財産すべてに課税されるわけではなく、相続財産の全体から債務や葬儀代を引くことができます。
非課税財産として差し引くことができ、差し引いた金額が正味の遺産の額になります。
この正味の遺産額から基礎控除を差し引いたのが、相続税の課税対象となる遺産総額です。
基礎控除を超えた場合の課税額は以下の表の通りです。

課税される遺産総額が、1,000万円であれば、100万円の相続税が課税され、5,000万円なら800万円です。
相続税の課税が必要な場合、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければいけないルールがあります。
10ヶ月間に相続財産や相続人の確定、遺産分割書の作成を行わなければならず、手続きには余裕がないため注意が必要です。
登録免許税
実家を相続する場合、相続税以外に名義変更で登録免許税が課税されます。
登録免許税は相続登記をする際に、課税される税金のことです。
法定相続人が相続登記をする際は、実家の固定資産税評価額の0.4%が登録免許税として課税されます。
相続人以外の方が遺言で相続する場合は、相続税が2割加算される場合があるため、注意が必要です。
相続税が発生しない場合
相続税が発生しない場合や相続が少額な場合でかつ特例を利用しないのであれば、相続税の申告自体は必要がありません。
実家を相続した場合はどんな選択肢がある?
実家を相続した場合の選択肢は以下の5つです。
●自分や親族が住む
●賃貸に出して家賃収入を得る
●売却してまとまった金額を得る
●アパートや駐車場などで土地活用をする
●相続放棄する
自分や親族が住む
実家を相続し、移り住みたい相続人がいる場合には、そのまま住み続ける方法があります。
誰かが住み続ければ、住宅用地の特例措置の適用も継続されるため、固定資産税が軽減されます。
相続人が複数いる場合は、誰かが実家に居住していると、相続が発生してもすぐに出ていくことは難しいですし、遺産分割協議中に退去を求めても、スムーズに進まないことが予想されます。
そのような場合は、代償分割や共有分割をうまく利用して、そのまま住み続けるのも方法の一つです。
敷地が広大で土地を分割しても誰かが実家にそのまま住めるのであれば、現物分割も検討できます。
賃貸に出して家賃収入を得る
実家が賃貸需要が高い地域にあり、大規模な修繕をしなくても住める状態ならば、賃貸に出すのがおすすめです。
賃貸に出すことで、家賃収入が得られ、空き家になり劣化が進んでいく心配もないでしょう。
ただし、大規模工事までいかなくても、賃貸に出すにはリフォームが必要な場合が多いです。
また、賃貸経営について知識が必要になりますので、注意が必要です。
入居者がしっかりと入居できる状況を作った上で、各種のトラブルを解決しつつ収益を得ていく必要があります。
入居者が決まるまでの期間は、貸主として、家の管理や税務処理をしなければなりません。
金銭的と時間にある程度余裕がある方でないと難しい場合もあります。
始めて賃貸経営をする人には、多少難しいところもありますので、不動産の管理会社などに相談しながら進めていきましょう。
売却してまとまった金額を得る
賃貸に出せないような空き家や、売却してまとまった現金がほしい場合は売却するのがおすすめです。
空き家をそのまま維持するには、草刈りなど敷地の手入れや室内の空気を入れ替えて腐食を防止したりするなどの管理が必要です。
また、実家が遠方にある場合は、実家にいくだけでも時間がかかるため、空気の入れ替えなどの管理自体ができないことも十分考えられます。
しかし、売却をすればまとまった現金が得られるので、相続人同士で分割しやすくなり管理の手間も省けます。
実家を手放してもよいと考えて、売却を選択する方はかなり多いです。
家や土地に資産価値がない場合は、売却がそもそもできない可能性もありますので注意が必要です。
売却が困難な場合は「相続土地国庫帰属制度」を利用する
もし実家の売却が困難な場合は、相続放棄や「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法もあります。
相続土地国庫帰属制度とは土地を国が引き取ってくれる制度のことです。
場合によっては、相続土地国庫帰属制度でも引き取れない土地の条件があります。
それは以下の条件です。
●建物がある土地
●担保権や使用収益権が設定されている土地
●他人の地用が予定されている土地
●土壌汚染されている土地
●境界が明らかでない土地
●所有権の存否や範囲について争いがある土地
このような条件に該当しなければ、土地を引き取ってもらえる可能性が高いですが、手数料がかかります。
その手数料は引き取ってもらう土地の地目や広さで変わるため、事前に手数料がどのくらいかかるのか確認するようにしましょう。
アパートや駐車場などで土地活用をする
実家に居住中もしくは、これから住む予定の親族がいない場合は建物を取り壊し、駐車場やアパート・マンションを建てたり、資材置き場にして貸し出す方法もあります。
立地条件が活用方法に適しているか、初期費用と運用費用の収支が合うかなど、赤字で失敗しないように事前の見極めが大切です。
また、土地活用するには、実家を解体したり建物を壊して更地にすると、資産税と都市計画税が上がることも注意しましょう。
相続放棄する
実家に住む予定がなく、資産価値もない物件で被相続人の資産が他にない、または負債があるような場合は、相続放棄をする方法もあります。
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も相続しないために行う手続きのことです。
相続放棄するには、相続の発生を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
なお、申し立てする前に遺産である現金の一部を使ってしまうなど、相続財産を使ってしまうと、相続する意思があるとみなされ、相続放棄できなくなるため注意しましょう。
相続放棄をするにあたり、相続財産清算人の選任の申し立てをして、家庭裁判所に選任されるまでは実家の管理責任が残ります。
相続財産清算人とは、相続財産を相続の利害関係者に分配したり、国庫に帰属させる人です。
申し立てをしてから、相続財産清算人が選任されるまでの期間は、大体2ヶ月かかることが多く、選任されるまでは相続放棄した人であっても実家の管理責任があります。
例えば、瓦が落ちて通行人に怪我を負わせたてしまい損が賠償請求される恐れがあるため、
しっかりと管理しておくことが大切です。
相続放棄しても管理責任までは逃れられないことを理解しましょう。
やってはいけない実家の相続3つの注意点
やってはいけない実家の相続の注意点は以下の3つです。
●実家の活用方法を決めずに相続する
●複数の相続人と共有名義にする
●実家を放置し続ける
実家の活用方法を決めずに相続する
実家の活用方法を決めてから相続しないと、空き家になり放置されて固定資産税やメンテナンス費用などコストだけがかかってしまいます。
事前に不動産に見合った活用方法を把握することが大切です。
例えば、建物の賃貸需要が低い地域では、賃貸を出しても入居者が見つかる可能性が低く、幹線道路や高速のインターチェンジなどが近くなければ資材置き場としても活用するのは難しいです。
事前に不動産に見合った活用方法を把握しておかずに、相続をしてから決めようとすると空き家期間が伸びることになります。
空き家になってしまうと、様々なリスクがありますので、事前に相続人同士で話し合って準備しておきましょう。
複数の相続人と共有名義にするい
共有名義とは、一つの不動産に対して複数の所有者がいる状態のことです。
これは様々なトラブルの元になる可能性が高いため、できれば避けた方が無難です。
共有したものは民法の規定により、その共有者であっても一人の判断で自由に使うことができません。
共有名義の不動産を売却したり、賃貸や貸し出しする時には他の共有者の同意が必要になります。
共有名義の不動産に対する行為は「保存行為」「管理行為」「変更行為」に分類され、それぞれ必要な同意の程度が異なります。
【保存行為】共有物の現状を維持するための行為
例)共有物の簡易的な修繕・不法占拠者への明け渡し請求
→共有者ひとりの意思で対応可
【管理行為】共有物を利用する行為
例)共有物の使用方法の決定・賃貸借契約の締結
→共有持ち分の過半数の同意が必要
【変更行為】共有物の形や性質を変更する行為
例)共有物の売却・建物の解体・建物の増改築
→共有者全員の同意が必要
例えば実家を売却する場合は、上記表の「変更行為」に該当するため、共有者全員の承諾がなければ売ることができません。
共有名義人の中で、現金化したい人と実家を残したい人がいると意見がかみ合わず、親族同士のトラブルに発展するケースがよくあります。
そのため、基本的には実家の名義は1人に決めた上で相続登記を行うようにしましょう。
実家を放置し続ける
不動産を保有すると、固定資産税や都市計画税などの税金が課税され、建物の補修費用もかかるため、建物と土地を維持するにはコストがかかります。
実家の活用を検討せずに放置していると、費用だけかさんでしまいます。
さらに放置した結果、建物の状態が悪くなってくると、自治体から特定空き家に指定されることもあります。
特定空き家とは、自治体が危険な状態にあると指定した空き家のことで、自治体から是正を求める指示や指令を受けてしまいます。
自治体からの指示を無視し続けて固定資産税が6倍になったケースもあります。
それでも無視し続けると最終的に、建物を強制的に解体されて解体費用を請求されます。
何もせずに放置し続けると様々なリスクが発生するので、活用方法を決めて手続き進めていきましょう。
まとめ
今回は、
●実家を相続する際の手順と、相続税の計算方法
●相続した実家の活用方法(居住・賃貸・売却など)
●相続時に陥りがちな3つの注意点
について解説しました。
実家の相続は複雑な手続きが必要で、相続税の申告には期限があります。
相続人同士でトラブルを避けるためにも、事前に活用方法を決め、共有名義を避け、放置しないことが重要です。
後悔しないために、不動産の専門家へ相談することも検討しましょう。
不動産のご相談ならウィローズ
資金計画の立て方が分からない、相談できるいい会社や担当者がいない
という方はぜひ武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せ下さい。
お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。
お気軽に公式LINEからご相談下さい。