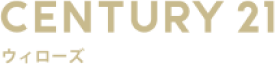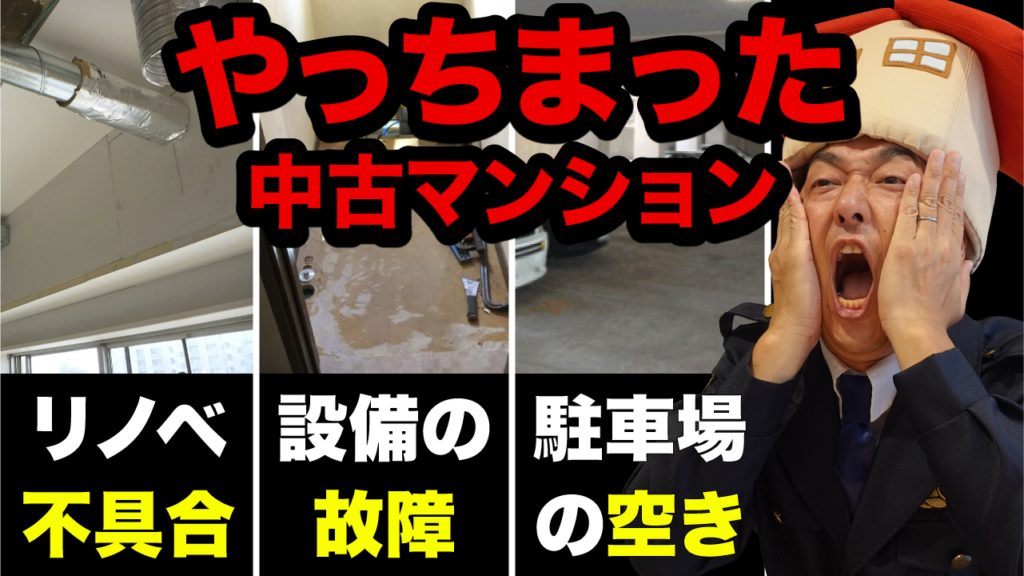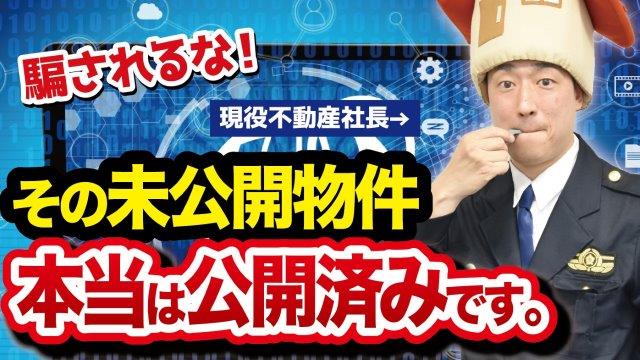はじめに
不動産を活用した相続税対策は富裕層の多くが実施していることをご存じの方も多いかと思います。
しかし、自分には関係がないと感じて、不動産が相続税対策としてどのように有効なのかを深く考える機会は少ないのではないでしょうか?
実際には、不動産と相続税の関係は多くの方にとって無関係ではありません。
本記事では、知っておくと損をしない「不動産と相続税」の基本的な仕組みから相続税の節税方法まで解説していきます。
本編
不動産の相続時に発生する税金
不動産を相続する際には、相続税以外にもさまざまな税金や手続きが発生します。
まず、相続によって不動産の名義を変更する場合には、「登録免許税」が必要です。
登録免許税は、相続登記の際に課される税金で、固定資産税評価額の0.4%が課税されます。
また、相続税の申告と納付には期限があり、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から10か月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると、「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが科される可能性があります。
不動産の相続税の計算方法
不動産を相続した際の相続税額は、いくつかのステップを踏んで計算されます。
まずは、被相続人のすべての財産を洗い出し、「プラスの財産(不動産・預金・有価証券など)」から「マイナスの財産(借入金・未払い費用など)」と「非課税財産(生命保険の一部など)」を差し引いて「正味の遺産総額」を算出します。
次に、相続税の「基礎控除額」を差し引きます。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められ、この控除を適用した後の金額が「課税遺産総額」となります。
この課税遺産総額を法定相続分で分割し、相続人ごとに国税庁の速算表を用いて相続税額を計算します。
最後に、各人の税額を合計することで、全体の相続税額が確定します。
不動産の相続税における土地・建物の評価方法
不動産を相続する際、相続税の計算で重要になるのが「評価額の算出方法」です。
現金とは異なり、不動産には独自の評価ルールが適用されるため、事前に把握しておくことが大切です。
まず、土地の評価には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
市街地などでは路線価方式が適用されることが多く、これは国税庁が公表する路線価(1㎡あたりの価格)に、土地の形状や接道状況などに応じた補正率をかけ、面積を乗じて評価額を算出します。
一方、郊外や地方では固定資産税評価額に一定倍率をかけて算出する「倍率方式」が使われることもあります。
次に、建物の評価は、原則として固定資産税評価額がそのまま相続税評価額として使用されます。
時価ではなく公的に定められた評価額を基にするため、実際の市場価格よりも低く見積もられるケースが一般的です。
このように、土地・建物と共に実勢価格より低く評価されやすいため、不動産相続税においては評価方法を正しく理解することで、大きな節税効果が期待できます。
相続を見据えた不動産の取得や資産配分を検討する際には、評価の仕組みを踏まえた計画が重要です。
不動産の相続税対策:評価・特例・活用術
現金ではない不動産相続による節税効果
不動産を相続する場合、相続税の計算には現金とは異なる評価方法が適用されます。
例えば、現金1億円を相続する場合は、そのまま相続資産1億円として課税対象になります。
しかし、不動産であれば、たとえ時価が1億円でも、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」によって評価されます。
例えば、品川区の戸建住宅を例にすると、購入価格に対して相続税評価額が35%ほどになるケースもあります。
現金で1億円を保有したまま相続が発生すれば、課税対象はそのまま1億円ですが、その現金で不動産を購入していれば、相続資産としての評価は3,000万円〜4,000万円に圧縮される可能性があります。
このような評価額と時価の乖離は、特に都心部で顕著です。
地方では評価と実勢価格の差が小さいことも多く、圧縮効果が限定的な場合があります。
小規模宅地等の特例の活用
相続税の節税において、重要なもう一つのポイントが「小規模宅地等の特例」です。
これは、被相続人が住んでいた土地や事業用(賃貸経営など)に供されていた土地に対して、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
例えば、実勢価格1億円のアパートを購入したとします。
土地7,000万円・建物3,000万円とした場合、土地は評価額が40%であれば2,800万円、建物は1,200万円に評価されます。
さらにこの土地が賃貸事業用であれば、小規模宅地の特例により評価額は50%減額され、土地評価額は1,400万円になります。
結果として、評価額の合計は2,600万円となり、現金で相続した場合と比べて大幅に圧縮されます。
長期修繕計画と修繕積立金のチェック
相続税の節税対策を考える際には、評価額や特例だけでなく、物件の維持管理コストにも目を向けることが大切です。
特にマンションや共同住宅の場合、長期修繕計画と修繕積立金の状況は将来の支出や資産価値に直結します。
長期修繕計画が適切に策定され、定期的に見直されている物件は、建物の劣化を防ぎ、資産価値を維持しやすくなります。
一方、修繕積立金が不足している場合は、相続後に一時金や急な値上げが発生し、思わぬ負担となる可能性があります。
不動産を相続する際には、物件の相続税評価額だけでなく、修繕積立金の残高や今後の修繕計画を確認することで、資産承継後のリスクを軽減できます。
これは、相続後の維持コストを見越した実質的な節税や資産管理にもつながる重要な視点です。
暦年贈与と相続時精算課税の比較
不動産を賃貸用に運用すれば、毎年家賃収入が得られますが、相続税の観点では現金が増えることで課税対象が再び増えてしまう可能性があります。
そこで活用したいのが「暦年贈与」の制度です。
暦年贈与では、1人あたり年間110万円までは非課税で贈与できます。
賃料収入を毎年家族へ贈与すれば、将来的な相続財産を減らしつつ、無税で資産を次世代に移転することが可能です。
この制度は、過去にも制度改正が行われてきましたが、令和6年(2024年)以降、以下のような見直しが発表されています。
持ち戻し期間が従来の3年から最大7年に延長
相続開始前の贈与のうち、死亡前7年間の贈与が相続財産に加算されるようになります。段階的な移行期を経て、2031年1月1日以降は7年ルールが完全適用される予定です。
4〜7年以内の贈与に対しては、合計100万円までの控除が認められる緩和措置
例えば、相続前6年間に毎年贈与した場合、合計600万円のうち100万円が控除され、相続財産に加算されるのは500万円です。
これらの改正により、暦年贈与だけの相続税対策では、従来より節税効果が縮小する傾向にあります。
特に不動産を購入した後に毎年110万円ずつ贈与する計画を立てる場合、持ち戻し期間の延長に伴い、早期スタートと計画的な贈与が必要になります。
令和6年度からは、暦年課税に代わり「相続時精算課税制度」の利用が再注目されています。
この制度では、子や孫への贈与について最大2,500万円まで非課税とされますが、相続時にその贈与を相続税の課税対象とする制度です。
さらに、改正により年間110万円の基礎控除が新設され、基礎控除内の贈与分は持ち戻し対象外となります。
また、この制度を選択すれば暦年贈与による生前贈与加算(持ち戻し)の対象外となる点も理解しておく必要があります。
不動産相続で押さえておきたいその他の節税対策
相続税の節税は、評価方法や特例、贈与制度の活用だけではありません。
状況に応じて、他の節税策も組み合わせることで、より効果的な対策が可能です。
生命保険の非課税枠の利用
相続人が受け取る生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる制度があります。
現金で残すよりも税負担を抑えられる場合があります。
不動産の共有名義化
相続人複数で不動産を共有名義にしておくことで、各相続人の取得分ごとに評価額を分散させ、税額を抑えられる場合があります。
不動産の組み替え
相続税評価額の高い土地を、評価額の低い収益物件や地方の不動産へ組み替えることで、評価の圧縮効果を得られます。
これらの対策は単独ではなく、評価方法の工夫や特例と組み合わせることで効果が高まります。
相続税の節税を最大化するには、早い段階で複数の選択肢を検討し、専門家とともに最適なプランを立てることが重要といえるでしょう。
まとめ
不動産を活用した相続税対策では、評価額の圧縮効果や小規模宅地の特例、暦年贈与の活用が大きなポイントとなります。
現金よりも不動産の方が相続評価が低くなる仕組みを理解し、制度改正にも対応しながら早めに対策を講じることが重要です。
最新の税制や手続きを正しく把握し、専門家のサポートを受けながら計画的に資産承継しましょう。
不動産のご相談ならウィローズ
資金計画の立て方が分からない、
相談できるいい会社や担当者がいないという方はぜひ
武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せください。
お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。お気軽に公式LINEからご相談ください。