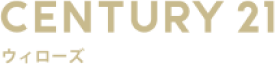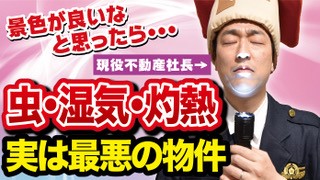はじめに
中古マンションを購入したものの、途中からランニングコストが上がってしまい、生活が破綻してしまうケースも多くあります。そのような物件を選ばないために、絶対選んではいけないマンションの特徴を押さえておきましょう。
本記事では、後悔しない中古マンション購入を実現するために、不動産のプロが「絶対買ってはいけない注意点」を9つ紹介します。
本編
後悔しない中古マンション購入を実現するための注意点9選!
管理費・修繕積立金の滞納額が100万円以上
マンションを適切に管理するためには、管理費・修繕積立金の徴収が必要不可欠です。
管理費・修繕積立金のお金を使って共有部分の管理や大規模修繕の工事を行うためです。
管理費・修繕積立金が計画通りに貯められておらず、100万円以上も滞納しているマンションは共用部分の管理が不十分の状態や大規模修繕工事ができない事態になりかねません。
100万円以上の滞納額は、管理組合が機能していない状態で問題になる裏付けになります。
管理費は
・エントランスの管理
・廊下の管理
・階段の管理
・エレベーター清掃と設備
・エレベーター定期点検
・管理人の人件費
などマンションの維持管理に使われます。
管理費の延滞が続くと管理の質が低下し、清掃が行き届かずに共用部分が汚れた状態のまま、その他にも、エレベーターが故障しても修理が後回しになる問題などが発生してしまいます。
修繕積立金は、約12年に1度行われる外壁や屋上などの大規模修繕工事のために積み立てられるお金です。
修繕積立金が不足すると工事が予定通り実施できず、
・建物の劣化が進んで雨漏りやひび割れ
・資産価値の低下につながる
可能性が高くなります。
そして、この滞納によって起こる最も深刻な問題が、”管理組合がしっかりと機能していない”ことです。
管理組合とは、管理費や修繕積立金の徴収・管理や修繕計画の策定と住民間のトラブル対応などマンションの管理と運営を担う住民組織です。
滞納が多いマンションでは、この管理組合が正常に機能していないため、計画通り貯められてないケースがあります。
管理組合が機能していない場合
・修繕計画が、適切に立てられない
・住民間のトラブルが解決しない
・セキュリティ対策が不十分
様々な問題が 発生するリスクが高まります。
このような理由で、管理費修繕積立金の滞納額が100万円以上あるマンションは住環境や資産価値が低下する可能性が高いため、気をつけましょう。
旧耐震基準のマンション
不動産経済研究所の首都圏新築分場マンション市場動向2024年のまとめというデータよると、2024年の東京23区の新築マンションの供給戸数は、30. 5%の8,275戸と公表されています。
(参考)不動産経済研究所|首都圏新築分場マンション市場動向2024年のまとめ
首都圏では、開発できる土地が少なくなっており、立地の良い物件ほど過去に開発された築年数が古いマンションが多いです。
すると、旧耐震基準を含む築古マンションを検討されている方もいるでしょう。
しかし、売却を前提に検討している場合は、旧耐震の物件はお勧めしません。
旧耐震基準とは1981年の5月31日以前に建築確認に適用されていた基準です。
旧耐震の物件の大きなデメリットは、
・将来的に買い手がつきにくい
・耐震面に不安を感じること
の2点です。
この旧耐震基準のマンションは、金融機関によって融資を制限している場合が多いです。
そもそも取り扱う銀行の数が少ないため、取り扱いがあったとしても審査が厳しく、金利が高い場合があります。
そうなると、自身で今購入する時はもちろんですが、将来、売却時に買い手が少なく売れにくい可能性や、売れたとしても相場よりも低い価格になる可能性があります。
気になる耐震性ですが、旧耐震基準は震度5程度の地震で倒壊しない、新耐震基準は震度6強から7程度でも倒壊しないレベルの基準です。
過去に発生した地震被害のデータを確認すると実は旧耐震と新体震の大きな差なかったとされています。
そのため、旧耐震だから必ずしも危険というわけではありませんが、万が一地震が発生した時に、本当に大丈夫なのかと不安を強く感じてしまう方は、旧耐震基準のマンションは避けたほうがいいでしょう。
駅から15分以上のマンション
不動産広告の表示規約では80mを徒歩1分で計算するように規定されています。
そのため、徒歩15分と表記されていれば、単純計算で駅まで1200mです。
しかし、一般的な人の歩行速度は時速3. 5km程度と言われており、1200m歩くには20分程度かかります。
また、信号待ちや坂道などによる減速もあります。
広告表記の計算上よりさらに1、2分かかることも考えられます。
つまり駅から徒歩15分以上となると、かなり実際の利便性は低くなります。
また、スーパーや公共施設などは、大体駅の近くにあることが多いので、生活のしやすさという点でも劣ります。
マンションには、多くの方が利便性の高さを求める人が多く、駅から遠い物件は敬遠されやすくなります。
敬遠されるということは、需要が低下し将来的に売却する際に、買い手がつきにくい可能性が高まります。散歩や歩くのが好きな場合は良いと思いますが、特に資産性を重視される場合は駅から徒歩15 分以上の物件は避けましょう。
定期借地権のマンション
定期借地権とは、地主が期限付きで土地の賃借を行い、そこに建てられた建物の所有者が土地代を支払うものです。
定期借地権付きのマンションは、地主から土地を借りてマンションが建築されるため土地の仕入代が販売価格に反映されません。
そのため通常のマンションよりも1割以上安く購入でき、買い手にとっては魅力的な価格の場合が多いです。
しかし、契約期間が満了になるとマンション自体を解体し、更地にしてから地主に返還することが法で決められており、返還する際には、地主から立退料などが支払われることはありません。
つまり、定期借権付きのマンションは購入し、自分が住んでる期間は自分の資産として考えることができますが、最終的に地主に返還しなければならないため、所有していたマイホームを手放す必要があります。
また毎月のランニングコストについても、住宅ローンの返済に加えて、土地価格の2〜3%の土地代を支払う必要があるので固定費が高くなる点も注意が必要です。
さらに、売却を検討する場合には、契約期間が残り少なくなると、次の買い手が見つけることがかなり難しく、資産価値が急落することもあります。
このように、特に終の棲家や資産性を重視して購入したい方は、デメリットが非常に大きいため、おすすめしません。
不動産経済研究所によると、今年に首都圏で供給される定期賃貸付きマンションは 2000戸に上る可能性があると言われ、2008年に供給された1200戸を大きく上回り過去最大規模になると予測されます。
そのため購入の選択肢の1つとして、検討することもあるかもしれませんが、注意が必要です。
住人だけで管理する自主管理のマンション
まず、マンションの管理形態やマンションの管理の業務について解説していきます。
マンションの管理形態は
●委託管理:管理会社に任せている管理形態
●自主管理:住人だけで管理していく管理形態
です。
マンション管理の業務は以下のものがあります。
●共用部分の清掃・修繕・点検などの建物維持管理
●管理費の徴収
●1年に1回決算業務などの会計や出納
●管理規約の制定
●予算管理などの理事会、総会運営
これらの仕事が適切に運営されていると、マンション全体の資産価値や快適な住環境を維持していけます。
自主管理は、煩雑な業務を自分たちだけで行います。
一見、住人で自発的に管理するのは、良いことに感じるかもしれません。
しかし、仕事や家事で忙しい一般の方が 専門的な知識が必要なマンション管理を適切に行わなければなりません。
・管理業務の経験のある方が住民におり、その方に業務が偏ってしまう
・一定の人が長期間役職を担うことで不正が行われてしまう
このような、不健在な管理体制 になる可能性が高いのです。
実際に平成6年から平成19年にかけて東京都世田谷区のマンションで行われたマンションで管理担当が管理費・修繕積金を横領し裁判になった事例もあります。
このように自主管理のマンションは適切な運営がされず、修繕工事が適切に行われず、管理修繕積立金の滞納が進み、マンションの質の低下や価値下落リスクが高い上に事件に発展するケースもあります。
自主管理の物件のマンションは買わないのが賢明です。
総戸数30戸以下のマンション
総戸数30戸以下の小規模なマンションは、1住戸あたりの管理費・修繕積金が高額です。
そして管理組合の運営が不安定になるという理由からお勧めできません。
マンションは、そこに暮らす住人が管理費・修繕積金を貯めければいけませんが、総戸数か少ないと1戸に対する負担割合が大きくなり、1人でも滞納すると滞納率が跳ね上がります。
すると、当初の計画通りに修繕が進められず劣化が進んでしまい、マンション全体の資産価値 が下落します。
また、最近はこの管理修繕金が建築材のインフレ傾向で高騰しています。小規模マンションは、その影響をより受けやすい可能性も高いです。
さらに管理組合も役員や理事を選任する際に、限られた人数の中から選ばれなければならないため、なり手不足で、運営が不安定になることがあります。
そのため、共用部分の管理がおろかになり、住民の意見が反映されにくくトラブルが発生しやすいです。
総戸数30戸以下の小規模マンションは、ランニングコストや快適性、資産性などのあらゆる面でリスクがあります。
事務所使用可能のマンション
事務所使用可能のマンションは登記簿上「共同住宅・事務所」と併記され事務所として利用できる物件です。
マンションの一室が事務所として利用できると、不特定多数の人が建物内に入ることになるため、犯罪リスクや騒音トラブル、入居者トラブルが発生するリスクが高まります。
警視庁の「住まいる防犯100番」によると、侵入犯罪の侵入口は 共同住宅の場合は表出口が 最も多く、6割程度占めていると公表されています。
(参考)警察庁|住まいる防犯100番
事務所使用可能で不特定多数の人が入り込む場合は、住民を把握しにくく、いつの間にか犯罪者が表から侵入されるケースもあります。
また飲食店が入居しているとゴミの匂いや虫が発生し、快適に過ごせなくなる恐れもありますので、事務所使用化のマンションはお勧めしません。
地上15階建てのマンション
マンションは建築基準法によって、31m・45m・60m・100mを区切りとし、建築基準法と消防法を、満たさなければならない条件が決まっています。
建物の高さが高くなるにつれ、基準が複雑になり設計と建築により、コストがかかる仕組みです。
その中で建築上、コストバランスが最も良いのが45mです。
費用体効果を最大限生かすために、45mギリギリに建築することが多く、マンションの階高は、3m程度に設定されます。
45mなら14階または15階建てになります。
実はこの違いが、住み心地に大きな違いを生みます。
建物には天井と床があるため、15階建て(3mの階高の天井高)の場合、天井高は約2.4mになります 。
2.4mの天井高は圧迫感を抱かない一般的な高さですが、構造に問題があります。
階高に余裕があれば、天井も床も二重になり上下からの騒音を和らげますが、階高に余裕がないと天井と床にクッションを貼り、クロスやフローリングをその上に敷くことになります。
この直貼りは騒音が上下に伝わりやすく、騒音トラブルが発生する確率が高まります。
また、階高に余裕があり、二重床構造となっている場合は、床下の空間に給水管、排水管、ガス管・電気配線などが通されていることが多く、リノベーションで間取りを大きく変更する際に配管の移動を比較的容易に行うことができます。
一方、直床の場合は配管が通っている部分のみ、二重床になっているため、後からリノベーションで、水回りを変更することが難しいです。
14階なら階高は、約3.21mと比較的余裕があり二重床で作られていることが多いですが、15階建ては約3mと余裕がなく、直貼りにしてる物件が多くあります。
このような理由から、無理に15階建てにした物件は、階高が圧迫されてしまい防音性能やリノベーションの自由度が低い可能性があり、注意する必要があります。
投資用不動産混合型マンション
住宅用と賃貸用のスペースが用意されたマンションにも注意が必要です。
2015年から2021年までは、日本のインフレ率は1%以下と低く推移していましたが、2022年以降2.0%以上も上昇しています。
不動産はインフレ率の上昇とともに、価格が上昇傾向にあるため、物価上昇対策として不動産投資が注目されています。
今後も不動産投資が活発化すれば、投資用不動混合型のマンションも増加していくと予想しています。
しかし、投資用不動産混合型のマンションは、注意すべき点が多いです。
投資目的の所有者はそこに住むわけではないため、マンションの管理を他人ごとと捉えているオーナーが多いです。
しかしマンション管理は、物件の資産価値や日々の暮らしの快適さに直結します。
それにも関わらず、管理費や修繕積立金の支払を滞納したり、共用部分の利用ルールを守らないことが起こると、マンションの資産価値が低下するだけではなく、居住者間のトラブルに発展する可能性があります。
また投資目的の所有者が多いマンションでは、賃貸住戸の入居者が頻繁に入れ替わるケース もよくあり、住民間のコミュニティが形成されにくく、ルールを守った暮らしや防犯面でも不安が残ります。
そのため、投資用不動産混合型のマンションは、できれば避けた方がよいでしょう。
まとめ
不動産のプロが絶対に買わないNGマンション9選は
●管理費・修繕積立金の滞納額が100万円以上あるマンション
●旧耐震基準のマンション
●駅から15分以上のマンション
●定期借地権付きのマンション
●自主管理のマンション
●総戸数30戸以下のマンション
●事務所使用可能のマンション
●地上15階建てのマンション
●投資用不動産混合型のマンション
です。
今回解説したポイントを参考に、中古マンション物件を選ぶ時に注意すべきポイントを押さえて、実際に物件を選ぶ時に参考にしてください。
不動産のご相談ならウィローズ
資金計画の立て方が分からない、相談できるいい会社や担当者がいない
という方はぜひ武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せ下さい。
お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。
お気軽に公式LINEからご相談下さい。