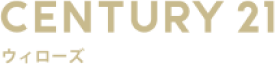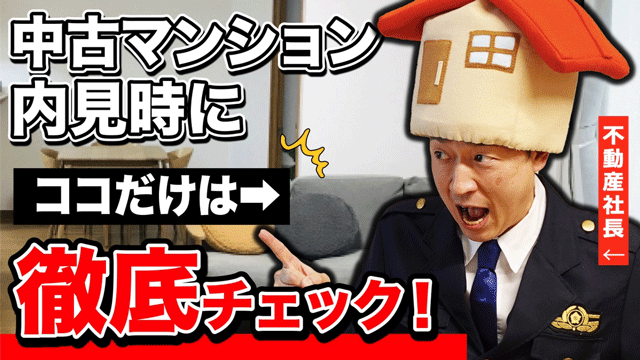はじめに
住宅ローンを取り巻く環境は、これまでとは大きく変化しています。
2024年における金利に関する大きな動きとして、以下の動きがありました。
・3月に日本銀行がマイナス金利政策の解除を発表した
・7月に政策金利を0.25%へ引き上げた
これらの影響を受けて、10月に入ると各金融機関で変動金利が引き上げられました。
一部のメガバンクでは、適用金利がネット銀行を下回るという状況も発生し、これまで「低金利の代名詞」とされてきたネット銀行の優位性が覆される場面も見られました。
情報を集めずに住宅ローンを選んでしまうと、数百万円単位で余計な利息を支払う可能性があり、後悔につながる恐れがあります。
そのような事態を避けるためにも、本記事で解説する、最新の金利動向を正しく把握し、慎重に住宅ローンを選びましょう。
本編
住宅ローン金利の仕組みと上がり方
住宅ローンの金利には、固定金利と変動金利があり、それぞれ金利の決定に用いられる指標が異なります。
そのため、両者が同じタイミングで上昇・下降するとは限りません。
住宅ローン金利の仕組みと上がり方について、ここでは、
・固定金利は10年国債利回りが指標
・変動金利は短期プライムレートが基準
について、解説していきます。
固定金利は10年国債利回りが指標
固定金利の基準となるのは「10年国債の利回り」です。
国債とは、国が資金を調達するために発行する債券で、購入者は投資額に応じて利子を受け取る仕組みになっています。
10年国債の利回りは、10年間にわたる国債の金利を示します。
この利回りは、米国債の金利に大きく影響されます。
米国債の金利が上昇し、日本国債との金利差が広がると、投資家は米国債を購入するようになります。
その結果、日本国債が売れにくくなり、日本政府は利回りを引き上げることで投資家の購入を促す必要が生じます。
実際に米国債の金利は2020年7月頃に1%を下回った後、上昇に転じ、2024年7月時点では4%を超えています。
日本の金融機関が固定金利を引き上げ始めた時期と一致しており、10年国債の利回りが米国債の動向に連動していることがわかります。
変動金利は短期プライムレートが基準
変動金利の基準となるのは「短期プライムレート」です。
これは、金融機関が優良企業向けの短期貸出に適用する最優遇金利を指します。
企業間取引(BtoB)で用いられるこの金利は、日銀の政策金利と連動しています。
そのため、変動金利は世界経済や外国債券の動向にはあまり影響を受けず、日銀の政策金利の変更に強く左右されます。
日銀が政策金利を低く維持する限り、短期プライムレートの上昇は起こりにくいと言えます。
しかし、2024年7月の日銀金融政策決定会合において、政策金利を0.25%に引き上げる決定がなされました。
この影響を受け、2009年1月から長らく変動のなかった短期プライムレートが、約15年ぶりに2024年9月に引き上げられました。
その結果、2024年10月以降、一部の金融機関では変動金利の引き上げが始まっています。
変動金利の現状と注意点
変動金利の現状と注意点として、ここでは、
・ネット銀行とメガバンクの金利が逆転するケース
・激化する金利の変動
・今後の変動金利の見通しは不透明
について、解説していきます。
ネット銀行とメガバンクの金利が逆転するケース
2024年10月に入り、主要銀行が相次いで住宅ローンの変動金利を0.15%引き上げました。
代表的な例として、三井住友銀行の変動金利は9月の0.475%から10月には0.625%へと上昇しました。
他の銀行でも同様の引き上げが見られる中、金利を据え置いた金融機関も存在します。
例えば、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ銀行、ソニー銀行では、9月と10月の変動金利に変更はありませんでした。
このような動きの結果として、一部のメガバンクの変動金利が、長らく低金利を牽引してきたネット銀行の金利を下回るという現象が発生しました。
特にauじぶん銀行は、9月までは0.329%という非常に低い変動金利を提供していましたが、10月には0.15%引き上げられ、0.479%となりました。
一方、三菱UFJ銀行は金利を据え置き、10月も0.345%で提供を続けており、最安クラスの変動金利となっています。
また、ネット銀行では、住信SBIネット銀行が0.298%から0.448%に、SBI新生銀行が0.29%から0.42%へと、それぞれ金利を引き上げました。
この動きにより、三菱UFJ銀行の金利の安さが際立つ結果となりました。
これまでネット銀行は、実店舗を持たず固定費を抑えられることで、低金利を実現してきました。
そのため、一般的には「ネット銀行=低金利」というイメージが定着していましたが、2024年10月にはその構図が逆転し、不動産業界でも大きな話題となりました。
実際に、10月以降はネット銀行の金利が上がった影響で、新規借り入れの相談が減少したという声もあります。
激化する金利の変動
11月に入っても、三菱UFJ銀行は主要銀行の中で最も低い変動金利を維持しており、10月と同じ0.345%が継続されています。
11月に変動金利に動きがあった主な金融機関は以下の通りです。
ソニー銀行:0.597% → 0.647%(+0.05%)
SBI新生銀行:0.420% → 0.430%(+0.01%)
楽天銀行:0.834% → 0.844%(+0.01%)
りそな銀行・埼玉りそな銀行:0.490% → 0.390%(−0.10%)
それでも、メガバンクの中で最も低い水準を維持しているのは、依然として三菱UFJ銀行です。
近年は低金利状態が続き、金利は毎月据え置かれるか、引き下げられる傾向にありました。
しかし、直近では1ヶ月単位で金利が上がったり下がったりするなど、変動が激しくなっており、これまでとは異なる動きが見られています。
今後の変動金利の見通しは不透明
ここまで解説してきました通り、今後の変動金利がどのように推移していくかについては、非常に不安定で、先行きが見えにくい状況が続いています。
住宅ローンの変動金利は、月末に翌月の金利が決定される仕組みとなっているため、現時点で金利が低い金融機関であっても、実際に借り入れする際に同じ水準であるとは限りません。
そのため、「この住宅ローンが最も金利が低いのでおすすめです」と断言できる状況にはありません。
このような不安定な金利の動きは、今後も半年から1年程度は続くと見られています。
住宅ローンの選択にあたっては、金利の変動リスクを考慮しながら、慎重に検討を進めることが重要と言えるでしょう。
固定金利タイプの特徴と動向
住宅ローンの固定金利状況として、ここでは、
・10年固定型は緩やかな上昇傾向
・35年固定(全期間固定)型の変動とメリット
・選ぶ際は長期の安定性も比較軸に
について、解説していきます。
10年固定型は緩やかな上昇傾向
10年固定金利に関しては、2024年11月に入り、多くの金融機関で0.01〜0.11%程度の金利引き上げが行われました。
10年固定金利は、一般的に10年国債の利回りを基準に設定されているため、日銀の利上げ期待や、欧米諸国の利下げなどを受けた細かな金利の変動が今後も反映されていく見通しです。
35年固定(全期間固定)型の変動とメリット
35年固定金利(全期間固定)についても、多くの金融機関で0.1%前後の引き上げが行われました。
一部では据え置きの金融機関もあります。
この35年固定金利は「超長期金利」の影響を受けており、超長期金利は約2年前から上昇基調に入っていました。
現在はおおむね2%前後で推移しており、大きな変動は見られないものの、今後は緩やかな上昇が続く可能性があるとされています。
とは言え、変動金利のように市場の影響を受けることがなく、毎月の返済額が一定となるため、将来の金利上昇に対する不安を抑えられる点はメリットです。
選ぶ際は長期の安定性も比較軸に
ここまで、変動金利および固定金利の最新の動きについて解説してきました。
特に変動金利は、2024年10月以降の動きが非常に不安定であり、この状況はしばらく続くと考えられています。
変動金利は一時的に低水準でも、将来的に金利が上昇すれば返済額が増えるリスクがあります。
一方、固定金利型は借入時点で返済額が確定するため、将来のライフプランを立てやすく、家計管理のしやすさにつながります。
特に子育てや老後を見据えた住宅ローン選びでは、「月々の返済額が変わらない安心感」や「総返済額の見通しやすさ」が大きなメリットとなります。
長期にわたる住宅ローンだからこそ、金利の安さだけでなく、安定性と将来の見通しも重視して比較することが大切と言えるでしょう。
住宅ローン選びで見るべき比較ポイント
住宅ローンの選び方は、数千万円単位の借り入れに直結するため、慎重に比較・検討する必要があります。
住宅ローン選びで見るべき比較ポイントとして、ここでは、
・金利タイプを確認する
・諸費用・手数料で総返済額を把握する
・返済方法と返済期間を比較する
・ローンの種類(民間/全期間固定/公的)を理解する
・団体信用生命保険(団信)の保障内容で比較する
・対面 or オンライン相談の利便性も要チェック
について、解説していきます。
金利タイプを確認する
住宅ローンには主に「変動金利」と「固定金利」があり、それぞれ金利の決まり方やリスクが異なります。
変動金利
変動金利は金利が低く設定される傾向にありますが、2024年10月以降、各金融機関で金利の引き上げが相次いでおり、今後の動向に注意が必要です。
金融機関によっては「5年ルール(5年間は返済額据え置き)」を設けており、急激な返済額の増加を一時的に防げます。
ただし、利息が増える分、元本の返済が遅れ、返済期間が延びる可能性があります。
固定金利
固定金利は金利が高めに設定されますが、返済額が一定のため、長期的な資金計画を立てやすい特徴があります。
特に、返済額を最初から確定させておきたい方には、全期間固定型(35年固定)も有効な選択肢です。
諸費用・手数料で総返済額を把握する
住宅ローンを比較する際には、金利だけでなく「諸費用」や「手数料」も含めた総返済額を把握することが重要です。
金融機関によっては、事務手数料や保証料、団体信用生命保険料などの設定が異なり、見落とすと数十万円以上の差が生まれることもあります。
例えば、事務手数料が「一律3万円」の銀行もあれば、「借入金額の2〜3%」と設定している銀行もあり、借入額が大きくなるほど負担も大きくなります。
また、金利に含まれていない別途費用として諸経費が発生する場合もあるため、金利だけで判断せず、必ず「総返済額」で比較することが大切です。
返済方法と返済期間を比較する
住宅ローンを選ぶ際は、金利タイプだけでなく「返済方法」と「返済期間」も比較することが重要です。
返済方法には主に「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。
元利均等返済は、毎月の返済額が一定で家計の見通しが立てやすい反面、元金の減り方が緩やかで利息の総額がやや多くなります。
一方、元金均等返済は毎月の元金返済額が一定のため、当初の返済負担は大きくなりますが、利息が抑えられるメリットがあります。
また、返済期間は一般的に最長35年まで選択可能ですが、期間を長く設定すれば月々の返済額は抑えられる一方で、総返済額は増加します。
反対に、短く設定すれば総返済額を抑えられますが、月々の負担は大きくなります。
将来の収入やライフプランを踏まえ、無理のない返済ができるよう、返済方法と返済期間のバランスを慎重に検討しましょう。
ローンの種類(民間/全期間固定/公的)を理解する
住宅ローンを比較・検討する際は、「どの種類のローンを選ぶか」も重要な判断軸です。住宅ローンには大きく分けて、民間ローン、全期間固定型ローン(例:フラット35)、そして公的融資(自治体・住宅金融支援機構など)の3種類があります。
民間ローンは銀行や信用金庫などが提供しており、金利優遇や付帯特典が多いのが特徴です。
金利タイプは変動・固定・固定期間選択型など多様で、自分のライフスタイルやリスク許容度に応じて選択できます。
一方、フラット35などの全期間固定型ローンは、借入時から完済まで金利が一定のため、長期的な返済計画を立てやすいのがメリットです。
将来の金利上昇リスクを避けたい方に向いています。
さらに、一定の条件を満たすと利用できる公的融資(自治体の住宅取得支援制度や住宅金融支援機構の一部融資)もあります。
所得制限や物件条件があるものの、金利や保証料などが優遇されるケースもあり、チェックしておく価値があります。
団体信用生命保険(団信)の保障内容で比較する
団体信用生命保険(団信)は、ローン契約者が死亡または高度障害になった場合、住宅ローン残高が保険によって完済される仕組みです。
加入条件と特約
・団信は基本的に住宅ローン契約の必須条件ですが、健康状態によっては加入できない場合もあります。
・フラット35のように団信加入が任意のローンも一部あります。
・ガン団信や三大疾病特約付きの団信などもあり、特約を付けると金利が上がることがあります。
現在加入している生命保険と団信の内容を照らし合わせ、無駄な重複がないように確認しましょう。
対面 or オンライン相談の利便性も要チェック
住宅ローンを検討する際は、金利や条件だけでなく、相談方法の利便性も比較ポイントのひとつです。
金融機関によって、対面相談に特化した店舗型サービスを提供しているところと、オンライン完結型の住宅ローンを展開しているネット銀行などがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
対面相談は、担当者から直接アドバイスを受けられる安心感があり、住宅ローンに不慣れな方や複雑な状況の方に向いています。
返済計画や商品比較について詳しく説明を受けられるため、不安を解消しやすい環境です。
一方、オンライン相談は自宅にいながら手軽に手続きができ、書類の提出から審査までをスピーディーに進められるのが特徴です。
忙しい共働き世帯や遠方に住む方にとっては、大きな利便性を持ちます。
ただし、オンライン型はサポートが限定的なケースもあるため、わからないことをすぐに確認したい方は、チャットサポートや電話窓口の有無も確認しておくと安心です。
自分のライフスタイルや希望するサポート体制に応じて、対面かオンラインかを比較し、使いやすい相談方法を選ぶことも、住宅ローン選びでは見落とせない大切なポイントです。
住宅ローンシミュレーションの方法
住宅ローンを検討する際は、金利の比較だけでなく「実際にどれだけの返済が必要か」を具体的に把握することが重要です。
そのためには、住宅ローンシミュレーションを活用することが有効です。
以下では、シミュレーションの流れと方法を解説していきます。
シミュレーションの目的を明確にする
住宅ローンシミュレーションには、主に以下の目的があります。
・毎月の返済額を把握するため
・ボーナス併用の返済プランを確認するため
・借入可能額の上限を知るため
・総返済額と利息負担の見通しを立てるため
金利の種類(変動/固定)や返済期間、借入金額によって大きく変わるため、条件ごとにシミュレーションすることがポイントです。
シミュレーションに必要な情報を準備する
シミュレーションする前に、以下の情報を準備しておきましょう。
・借入予定金額:3,000万円など
・借入期間:35年など
・金利タイプ:変動金利/10年固定など
・想定適用金利:0.5%、1.0%など
・ボーナス併用の有無:あり/なし
・頭金の額:500万円など
※シミュレーションサイトによっては、年収や支出を入力して「借入可能額」を算出する機能もあります。
金融機関や不動産ポータルサイトのツールを活用する
以下のようなローンシミュレーターがよく使われます。
・各銀行の公式サイト(例:三菱UFJ銀行、住信SBIネット銀行など)
・不動産ポータル(例:SUUMO、LIFULL HOME’S、アットホーム)
これらのツールでは、「毎月の返済額」「年間返済額」「総返済額」「利息総額」などが自動で算出されます。
複数パターンを比較しながら、自分にとって無理のない返済プランを見つけましょう。
シミュレーション結果をもとに資金計画を見直す
シミュレーションした結果、以下のような判断材料になります。
・返済額が多すぎる場合:借入額の見直しや返済期間の延長を検討
・余裕がある場合:返済期間を短縮することで利息を圧縮することも可能
・頭金を増やすかどうか、ボーナス併用にするかも見直し対象に
ここで、家計全体のバランスを見ながら「月々の支払可能額」を明確にしておくことが重要です。
事前審査の申し込みで選択肢を絞り込む
シミュレーションはあくまで目安です。
実際に借入できる金額や金利は、各金融機関の審査によって決まります。
そのため、複数の金融機関に事前審査を申し込むことで、正式な「適用金利」と「借入限度額」が明確になり、より現実的な返済計画を立てられます。
まとめ
住宅ローンを選ぶ際には、信頼できるパートナーの存在が非常に重要です。
現在の金利状況を見ると、固定金利・変動金利両方ともに緩やかに上昇傾向にはありますが、長期的に見れば依然として低水準で推移しています。
過度に不安を抱えることなく、最新の金利情報をしっかりと収集し、自分に合った金融機関を選ぶことが大切です。
金利が比較的低い今のうちに住宅ローンを借り始めておくことで、元本(残債)を早く減ららし、将来的な金利上昇リスクを軽減できます。
数年後に金利がさらに上昇し、「あの時に借りておけばよかった」と後悔する可能性もあります。
また、将来のライフスタイルや収入の変化を見据えて、無理のない資金計画を事前に立てておくことで、多少の金利上昇にも柔軟に対応できます。
住宅ローンの返済において、資金計画は欠かせない要素です。
あらかじめファイナンシャルプランナーや信頼できる不動産会社の担当者と相談し、自分に合った住宅ローンの設計を進めていくようにしましょう。
(参考)【初心者必見】不動産会社社長が語る!中古マンション購入の入門知識を1時間で徹底解説!
不動産のご相談ならウィローズ
資金計画の立て方が分からない、
相談できるいい会社や担当者がいないという方はぜひ
武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せください。
お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。お気軽に公式LINEからご相談ください。