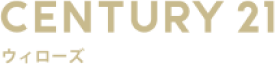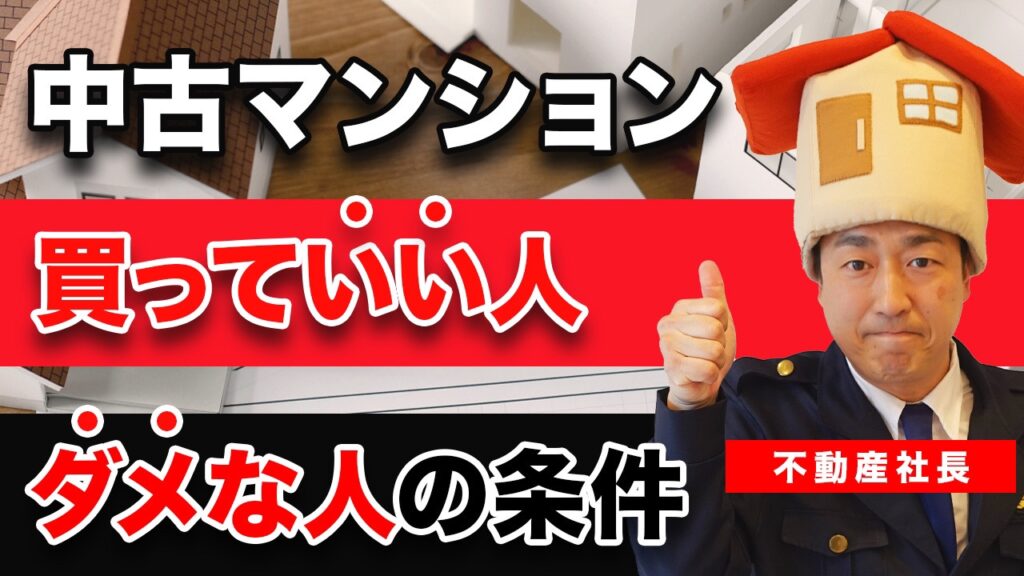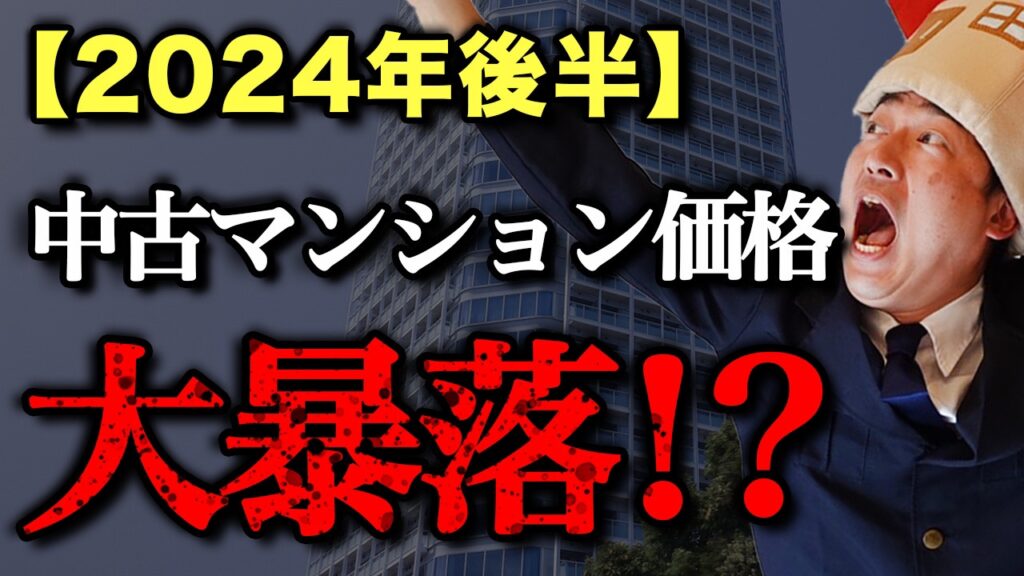はじめに
ここ数年、集中豪雨による河川の決壊や住宅の冠水がニュースで取り上げられることが増えています。不動産を購入する際には、そのエリアが水害に強いかどうかが気になる方も多いでしょう。多くの方は、自治体が作成しているハザードマップを確認しますが、色が付いている場所が必ずしも購入に適さないとは限りません。
本記事では、水害が増えている背景やハザードマップの基本について、解説していきます。
ハザードマップが作成された背景を理解し、購入の判断材料にしましょう。
本編
ハザードマップの種類と特徴
ハザードマップとは、自然災害による被害が想定される範囲や程度を示した地図のことです。
ひと口にハザードマップといっても種類は複数あり、対象となる災害によって示される内容が異なります。
洪水・内水氾濫ハザードマップ
洪水・内水氾濫ハザードマップは、大雨や河川の氾濫によって浸水が想定される区域を示した地図です。
河川の堤防決壊による「洪水」と、下水道や排水設備の処理能力を超えた雨水による「内水氾濫」の両方を対象としています。
浸水の深さや範囲が色分けされているため、自宅や購入予定の不動産がどの程度の浸水リスクを抱えているかを具体的に確認できます。
土砂災害ハザードマップ
土砂災害ハザードマップは、大雨や地震などによって発生する土石流・がけ崩れ・地すべりの危険区域を示した地図です。
山間部や斜面地に近いエリアでは特に重要で、土砂が到達する範囲や警戒区域が分かるようになっています。
住宅購入や土地利用を考える際には、被害想定区域に含まれていないかを事前に確認することが重要です。
津波ハザードマップ
津波ハザードマップは、地震発生時に想定される津波の高さや浸水範囲を示した地図です。
沿岸部や海抜の低い地域での居住や不動産購入においては確認しておくべき情報です。
浸水の想定深さだけでなく、津波到達までの時間が記載されている場合もあり、迅速な避難行動を取るための判断材料となります。
火山ハザードマップ
火山ハザードマップは、火山の噴火により発生する溶岩流・火砕流・降灰などの影響が及ぶ範囲を示した地図です。
日本は火山の多い国であり、特に活火山周辺の地域では、居住や土地利用の安全性を確認するために重要です。
火山ごとの特性に応じた被害想定が反映されているため、地域ごとに内容が大きく異なるのが特徴です。
地震動予測地図
地震動予測地図は、地震発生時にどの程度の揺れが予測されるかを示した地図です。
地域ごとの地盤特性や過去の地震データをもとに作成されており、震度の大きさや液状化の可能性が確認できます。
建物の耐震性や土地の選定において重要な判断材料となるため、不動産購入を検討する際には確認しておきたい情報です。
防災マップとの違い
防災マップとは避難所や避難経路、AEDの設置場所など、災害が発生した際の避難行動に必要な情報をまとめた地図です。
ハザードマップとの大きな違いは、ハザードマップは「被害の予測」を目的としているのに対し、防災マップは「避難の支援」を目的としている点にあります。
ハザードマップを見ることで災害リスクを把握し、防災マップを確認することで実際の避難行動に備えられます。
つまり、「ハザードマップとは」リスクを可視化するための地図であり、「防災マップ」と併せて利用することで、災害への備えをより確実なものにすることが可能となります。
なお、避難の際に大切なのは、複数のルートを確認しておくことです。
災害の種類によって安全な道が変わる可能性があるため、1つのルートに頼らず、いくつかの選択肢を持っておくことが推奨されます。
また、実際に歩いてみて所要時間や危険箇所を確認しておくと、より現実的な避難計画につながります。
洪水・内水氾濫ハザードマップの見方|浸水深の読み方と注意点
水害ハザードマップとは、行政が発行している地図で、過去の豪雨災害時と同程度の大雨や大きな河川の氾濫が起きた際に、浸水する可能性がある地域を色分けして表示したものです。

色の付いたエリアは浸水の恐れがある場所として注意喚起されています。
色ごとに浸水の深さが異なり、「床下浸水」から「2m以上」など段階的に想定が示されています。
下記は想定される浸水深と被害イメージの目安です。
浸水深と被害の目安(国交省の想定例)
| 浸水深 | 色の目安 | 被害イメージ |
| 床下浸水未満 (0.3m未満) |
黄色 | 床下まで水が到達するが、生活空間への影響は少ない |
| 0.3〜0.5m | 黄緑 | 家具の脚が濡れる、畳やカーペットに被害 |
| 0.5〜1.0m | 橙色 | 床上浸水、家電や家具が被害を受ける |
| 1.0〜2.0m | 赤 | 生活空間がほぼ水没、1階は使用不可 |
| 2.0m以上 | 濃赤 | 建物1階が完全に水没、2階以上への避難が必要 |
下図を拡大すると、黄色いエリアがいくつか確認できます。
これらは「危険」または「注意が必要」とされる区域を示しています。

一戸建てや土地を購入する方はもちろん、マンション購入を検討する場合にもハザードマップの確認は重要です。
近年では浸水が原因でマンション全体が被害を受ける事例も発生しており、購入を検討する際に「物件が色付きエリアにあるかどうか」を気にする方が増えています。
実際に、気に入った物件であってもハザードマップで色が付いていたために契約を取りやめるケースもあります。
こうした判断は理解できますが、ハザードマップだけを理由に契約を断念してしまうのは必ずしも適切とは言えません。
また、ハザードマップで色がついていない地域だからといって、必ずしも安全とは限りません。
過去に浸水履歴があるかどうかを、市区町村の窓口で確認しておくと安心でしょう。
水害ハザードマップ作成の背景と水害増加の要因
気候変動の影響
近年、水害ハザードマップが作成されている背景には、気候変動の影響があります。
集中豪雨による河川の氾濫や市街地の冠水はニュースでも頻繁に取り上げられています。
これは地球温暖化の影響で、日本が亜熱帯化しつつあり、想定を超える降雨量が発生しているためです。
その結果、堤防が決壊したり、排水が間に合わず冠水が起きるケースが増えています。
都市化の影響
もう一つの要因は都市化です。
かつて雨水は畑や庭から地中に浸透していましたが、都市開発が進み、コンクリートやアスファルトが増加しました。
そのため、雨水が排水管に集中して流れ込み、処理が追いつかず冠水を引き起こすようになっています。
国が水害ハザードマップの作成を促した理由
気候変動や都市化といった要因は、市民が直接防ぐことはできません。
道路の排水管を太くするには長い年月と膨大な税金が必要です。
そこで国土交通省は2015年(平成27年)に、危険性があると考えられるエリアについて「ここは冠水の可能性がある」と住民に周知するため、自治体に水害ハザードマップを作成するよう指示しました。
あらかじめ危険を知らせることで、購入や居住の判断材料となり、また災害時にも心構えができるようにすることが目的でした。
【国交省公式】ハザードマップポータルサイトの使い方
国土交通省が提供する「ハザードマップポータルサイト」は、全国の災害リスクをまとめて確認できる便利なツールです。
ここでは大きく分けて2つの機能が利用できます。
重ねるハザードマップ
洪水・土砂災害・津波など複数の災害リスクを地図上に重ねて表示できる機能です。
自宅や購入予定の不動産周辺に、どのような複合的リスクがあるのかを一目で把握できます。
わがまちハザードマップ
自治体ごとに公開されている詳細なハザードマップにアクセスできる機能です。
地域特有のリスクや避難所などの情報も確認できるため、より実生活に即した防災対策に役立ちます。
このように「ハザードマップとは」災害リスクを可視化する地図ですが、ポータルサイトを活用することで、より幅広い情報を入手し、自分や家族を守るための判断材料にできます。
ハザードマップの入手方法と更新確認の重要性
ハザードマップの代表的な入手方法は以下の3つです。
市区町村役所の窓口
紙のハザードマップを配布しており、地域の最新情報を直接入手できます。
自治体の公式ウェブサイト
PDFなどの形で公開されていることが多く、自宅から簡単にダウンロード可能です。
国土交通省のハザードマップポータルサイト
全国の自治体が作成したマップにアクセスでき、上記のとおり複数の災害リスクを一括で確認できます。
また、ハザードマップは一度作られたら終わりではなく、想定される災害規模の見直しや新しい調査データの反映により、随時更新されています。
そのため、常に最新版を確認することが重要です。
特に不動産の購入や引っ越しを検討している場合は、最新情報をもとに判断することで、将来的なリスク回避につながります。
企業や家庭の防災計画(BCP)へのハザードマップ活用方法
ハザードマップは、個人だけでなく企業や家庭の防災計画にも活用できます。
特に企業においては、事業継続計画(BCP)を策定する際の重要な資料となります。
例えば、オフィスや工場が浸水想定区域にある場合、代替拠点の確保や従業員の避難経路の設定が必要です。
また、物流拠点や取引先が被害を受けた際の対応策を検討する上でも、ハザードマップは判断材料として有効です。
家庭においても同様に、居住地周辺のリスクを確認し、家族の避難場所や連絡手段を事前に決めておくことで、災害時の混乱を防げます。
このように「ハザードマップとは」災害リスクを知るだけでなく、事前に具体的な行動計画を立てるための基盤となるものです。
企業も家庭も積極的に活用することで、被害を最小限に抑える備えが可能になります。
よくある質問(FAQ)
ハザードマップはどれくらいの頻度で更新される?
ハザードマップの更新頻度は一律ではなく、自治体によって異なります。
新しい調査結果や災害の経験をもとに随時改訂されるため、数年ごとに更新されるケースが一般的です。
最新情報は自治体の公式サイトや国土交通省のハザードマップポータルサイトで確認しましょう。
ハザードマップに載っていない場所は安全?
ハザードマップに色が付いていない地域であっても、必ずしも安全とは限りません。
過去に大きな災害が起きていないだけで、想定外の豪雨や地震などによって被害が発生する可能性があります。
念のため市区町村の窓口で災害履歴を確認したり、地形や周辺環境を調べることが大切です。
ハザードマップはスマホアプリで確認できる?
ハザードマップはスマホアプリやウェブサイトでも確認できます。
特に国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」はスマホからの利用にも対応しており、現在地周辺のリスクを手軽にチェックできます。
自治体によっては独自の防災アプリを提供している場合もあるため、日常的に利用できるツールとして活用すると便利です。
まとめ
ハザードマップとは、洪水や土砂災害、地震などの自然災害による被害が想定される区域を示す地図であり、不動産購入や日常の防災対策に欠かせない情報源です。
種類によって示されるリスクは異なり、防災マップと併せて活用することで、災害予測から避難行動まで一貫して備えられます。
国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」を利用すれば、複数のリスクを重ねて確認できるほか、自治体ごとの詳細情報も入手できます。
入手先は役所や公式サイトなどさまざまですが、常に最新版を確認することが重要です。
確認の際には浸水深や色の意味を理解し、色が付いていない場所でも油断しないことが大切です。
また、避難ルートや避難場所を事前に把握しておくことで、災害発生時の行動をスムーズに取れます。
さらに、企業においては事業継続計画(BCP)、家庭においては家族の防災計画に活用でき、被害を最小限に抑える行動計画づくりに直結します。
このように「ハザードマップとは」、災害リスクを「知る」だけでなく「備える」ために活用すべき実践的なツールであり、安全・安心な暮らしを守るための強力な指針となります。
不動産のご相談ならウィローズ
資金計画の立て方が分からない、
相談できるいい会社や担当者がいないという方はぜひ
武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せください。
お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。お気軽に公式LINEからご相談ください。