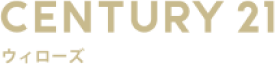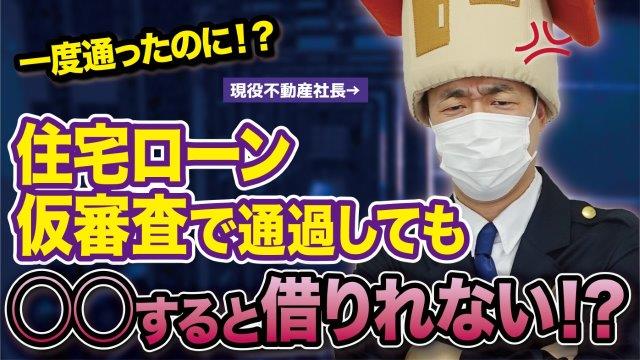はじめに
住宅を購入すると、毎年支払う必要があるのが固定資産税です。
少しでも税額を抑えたいと考える方は多いでしょう。
固定資産税には、小規模住宅用地の特例・新築住宅の減額・リフォーム減税・土地分筆・評価額見直しなど、複数の節税方法があります。
本記事では、固定資産税の計算方法から軽減制度の条件・申請手順まで、固定資産税を安くする方法を解説します。
本編
固定資産税の計算方法と免税条件
固定資産税の計算式と税率
建物や土地を所有している場合、毎年「固定資産税」が課税されます。
この固定資産税は、「固定資産税評価額(課税標準)」をもとに以下の計算式で算出されます。
固定資産税評価額 × 1.4%
固定資産税評価額の算出方法
固定資産税評価額は建物と土地で別々に評価されます。
建物:新築時が最も高く、築年数とともに下がる
土地:公示地価の約7割(地域によって5割程度の場合もあり)
評価額は3年ごとに見直されるため、評価のタイミングや地価の変動によって税額が変わることがあります。
評価額に誤りがあると税額も変わるため、納税通知書は必ず確認しましょう。
固定資産税が免税になるケース
固定資産税には、一定の条件を満たすことで課税されない(免税となる)ケースがあります。
課税標準額が一定以下の場合
土地や建物の課税標準額(固定資産税評価額)が以下の基準を下回ると、固定資産税は課税されません。
・土地:30万円未満
・家屋:20万円未満
公共性のある私道や公園
私道や地域に提供されている公園など、公共の利用に供されている土地は、非課税の対象になることがあります。用途や構造によって判断されるため、詳細は自治体に確認が必要です。
災害による損壊・滅失
地震・火災・風水害などの災害により、土地や家屋が著しく損壊した場合は、免税や減免の対象となることがあります。申請には、罹災証明書などの提出が必要です。
こうした免税対象に該当するかどうかは、自己申告が必要なケースが多いため、放置せずに自治体へ確認・申請することが重要です。
住宅用地の特例で節税
小規模住宅用地の特例(200㎡以下は評価額が1/6に)
住宅用地のうち、200㎡以下の部分については「小規模住宅用地」として扱われ、固定資産税評価額が6分の1に軽減されます。
この特例は、土地の所有者にとって非常に大きな節税効果があり、特に地価の高い都市部では税額軽減のメリットが顕著です。
一般住宅用地の特例(200㎡超の部分は評価額が1/3に)
住宅用地の200㎡を超える部分については、「一般住宅用地」として評価され、固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
小規模住宅用地と一般住宅用地の区分を正しく把握し、適用漏れがないようにすることが重要です。
そのため、登記簿と現状との「差異」を確認することが重要です。
納税通知書や登記簿に記載された内容と実際の土地面積や用途に相違がないか確認することで、本来適用される減税措置の漏れを防止できます。
特例適用条件と申請
小規模住宅用地や一般住宅用地の特例を受けるには、住宅が建っていることや住宅の敷地として利用していることなど、一定の条件を満たす必要があります。
主な条件は以下のとおりです。
・住宅1戸につき、その敷地として利用していること
・住宅の延床面積が50㎡以上、または共有持分に応じた面積を満たすこと
・マンションの場合は敷地の持分割合で按分された面積が適用されること
これらの特例は、多くの自治体で固定資産税の課税時に自動適用されますが、土地の利用形態に変更があった場合や新たに住宅を建てた場合は申請が必要になるケースがあります。
申請時には、住宅の登記事項証明書や建物図面、現況がわかる写真などを求められることがあります。
新築・長期優良住宅の軽減措置
新築住宅の固定資産税が1/2になる条件
新築住宅は、新築時に固定資産税の軽減措置が適用されます。
「新築住宅に対する税額の軽減措置」により、建物にかかる固定資産税が一定期間1/2に軽減されます。
・戸建:3年間(耐火・準耐火は5年)
・マンション:5年間
認定長期優良住宅の固定資産税軽減と期間
認定長期優良住宅とは、耐久性や省エネ性、維持管理のしやすさなど、国が定める基準を満たした優良な住宅に対して認定される制度です。
この認定を受けることで、通常の新築住宅よりも固定資産税の軽減期間が延長されます。
・戸建:5年間(+2年)
・マンション:7年間(+2年)
特例が重複しない場合の注意点
固定資産税の軽減措置には、小規模住宅用地の特例や新築住宅の減額、認定長期優良住宅の軽減など複数の制度がありますが、内容によっては同時に適用されないケースがあります。
例えば、新築住宅の1/2減額と長期優良住宅の軽減は「期間延長」という形で連動しますが、別の軽減措置と重複して税額がさらに減るわけではありません。
また、同じ固定資産に対して、異なる特例の適用対象期間が重なる場合は、より有利な方が優先される仕組みです。
特例が重複しないため、「適用されると思っていた減額が受けられなかった」というトラブルも起こり得ます。
制度ごとの条件や適用順序は自治体によって異なる場合があるため、事前に資産税課へ確認し、最も効果的に固定資産税を安くする方法を選ぶことが重要です。
リフォーム減税で税負担を軽くする
耐震リフォームによる軽減措置
旧耐震基準で建てられた住宅に対し、現行の耐震基準に適合するよう50万円以上の耐震リフォームを実施した場合、翌年度の固定資産税が1/3に軽減されます。
バリアフリーリフォームによる軽減措置
通路の拡幅、階段の勾配緩和、浴室やトイレの改良などを50万円以上かけて工事した場合、翌年度の固定資産税が1/3に軽減されます。
省エネリフォームによる軽減措置
窓の断熱改修、床・天井・壁の断熱工事などに50万円以上の費用をかけて行った場合、翌年度の固定資産税が1/3に軽減されます。
認定長期優良住宅水準へのリフォームによる軽減措置
上記の省エネ・バリアフリー・耐震リフォームを、認定長期優良住宅相当の基準で施工した場合は、翌年度の固定資産税が1/3ではなく、2/3に軽減される場合もあります。
リフォーム工事を検討している場合は、制度の条件を事前に確認し、適用可否をチェックしておくことが重要です。
各リフォーム軽減措置の要件と申請方法
主な要件
耐震リフォーム:旧耐震基準で建てられた住宅を、現行耐震基準に適合するよう工事を行うこと。工事費用が50万円以上であること。
バリアフリーリフォーム:通路や出入口の拡幅、階段勾配の緩和、浴室やトイレの改良など、高齢者や障害者の居住性を高める工事であること。費用は50万円以上。
省エネリフォーム:窓の断熱改修や壁・天井・床の断熱工事など、省エネルギー性能を高める工事であること。費用は50万円以上。
認定長期優良住宅水準へのリフォーム:省エネ・バリアフリー・耐震のいずれかを、長期優良住宅相当の基準で施工すること。
申請方法
1.工事完了後、翌年度の固定資産税に反映させるため、自治体の資産税課へ申請書を提出する。
2.必要書類は、工事契約書、領収書、工事の内容がわかる図面や仕様書、施工前後の写真など。
3.一部の制度では、建築士や指定検査機関による証明書が必要となる。
これらの軽減措置は自己申告制のため、申請を行わなければ適用されません。
固定資産税を安くする方法として確実に活用するためには、工事計画の段階から施工業者や建築士と連携し、必要書類を整えておくことが重要です。
その他の節税方法
土地の分筆
土地の利用状況や課税内容を見直すことで、固定資産税を抑えられるケースがあります。
なかでも注目したいのが、「分筆(ぶんぴつ)」という手続きです。
分筆とは、1つの土地を複数に分けて登記し直すことを指します。
これにより、以下のような固定資産税の軽減が見込まれる場合があります。
・小規模住宅用地の特例が適用されやすくなる
・土地の一部が非課税の対象となる可能性がある
・評価額が再計算され、結果として税額が下がることがある
ただし、分筆には測量費や登記費用などのコストがかかるため、実際に固定資産税がどの程度軽減されるかを事前にシミュレーションすることが重要です。
固定資産税を安くする方法として、土地の分筆は見落とされがちですが、適切に活用すれば大きな節税効果を得られる可能性があります。
検討の際は、司法書士や不動産の専門家に相談しながら進めましょう。
固定資産税評価額の見直しと不服申立て
固定資産税は、固定資産税評価額をもとに算出されるため、評価額が高すぎる場合には税負担も大きくなります。
評価額は原則3年ごとに見直されますが、その内容に誤りや不当な高評価があると感じた場合は、不服申立て(審査申出)を行うことができます。
手続きの流れは以下の通りです。
1.固定資産課税台帳の閲覧で評価内容を確認
2.誤りがあると考えられる場合、固定資産評価審査委員会へ申出を提出
3.申出期間は、原則として課税明細書の交付を受けた日の翌日から3か月以内
不服申立てには、土地や建物の図面、売買事例、地価公示価格などの根拠資料を揃えることが重要です。
評価額を正しく見直すことで、固定資産税を安くすることにつながりますので、税額に疑問を感じた場合は早めに行動しましょう。
固定資産税の軽減には届出が必要
届出の種類と期限
固定資産税の軽減措置を受けるためには、工事内容や土地利用の変更などに応じた届出が必要です。
代表的なものには、小規模住宅用地の特例、新築住宅の減額申請、耐震・省エネ・バリアフリーリフォームの軽減申請などがあります。
届出期限は制度によって異なりますが、多くの場合は軽減対象となる年度の初日(4月1日)までに自治体へ申請する必要があります。
リフォーム軽減の場合は、工事完了から一定期間内に申請しなければなりません。
事前に自治体の資産税課で期限を確認し、必要書類をそろえて提出しましょう。
届出しない場合のリスク
軽減措置の多くは自己申告制であり、届出をしなければ自動で適用されません。
そのため、申請を怠ると本来受けられるはずの減税が適用されず、結果として税負担が大きくなります。
また、届出期限を過ぎてしまうと、その年度は軽減を受けられず、翌年度以降にしか反映されないケースもあります。
固定資産税を安くするためには、条件を満たすだけでなく、期限内の届出が不可欠です。
まとめ
固定資産税は毎年かかるため、正しい知識を持ち、活用できる軽減措置を把握しておくことが重要です。
小規模宅地や新築住宅の特例、省エネ・バリアフリー・耐震リフォームによる減税、さらには長期優良住宅の認定や土地の分筆といった対策まで、節税の方法は多岐にわたります。
届出や申請を忘れず、必要書類を整えることで、固定資産税を安くする効果的な手段を確実に活かしましょう。
不動産のご相談ならウィローズ
資金計画の立て方が分からない、
相談できるいい会社や担当者がいないという方はぜひ
武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せください。
お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。お気軽に公式LINEからご相談ください。